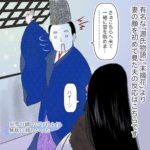謎に包まれたテレビ型の石を見に行く! 生石神社/兵庫県高砂市
神社仏閣好きラノベ作家 森田季節の推し寺社ぶらり【第2回】
津々浦々の神社・仏閣を訪ね歩くことを趣味にしているライトノベル作家の森田季節さん。全国に約16万もあるという神社・仏閣の中から、知見を生かしたマニアックな視点で神社・仏閣を紹介! あなたをめくるめく寺社探訪の旅に招待します。興味を持った方はぜひ現地に訪れてみよう。

社殿裏手に現れる巨石。自然石ではなくて加工されているところにオーパーツ的な違和感がある。Yama / PIXTA(ピクスタ)
■2キロ離れた駅名にも採用される「石の宝殿」
巨石が境内にある寺社は日本各地にありますが、少なくとも奈良時代から人に「なんだこれ?」と思わせ続けてきた、かなり特殊な神社を紹介します。
大阪駅からは西に約1時間、姫路駅からは約15分電車に乗ると宝殿という駅に着きます。駅から約2キロ歩くと生石(おおしこ)神社というなかなか立派な神社に到着します。長い石段をようやく上りきった先の社殿裏手に目的の巨石が存在します。
眼前にいきなり注連縄の張られた四角い石が現れるので、なかなか衝撃的です! これが「石の宝殿」と呼ばれるもので、見るからに自然石ではなく、人の手で加工された立方体です。言うまでもなく、駅名もこの石にちなみます。2キロ離れていても駅名に採用されるぐらいにはインパクトのあるものです。
大きな自然石が信仰対象になっている場所は無数にありますが、ここの場合、完全に加工された謎の石です。背後の高台に登って見下ろすこともできますが、これって昔のブラウン管テレビっぽい形ですよね。しかも、石の下は水が入っていて、池のようになっていて、水に浮いているようにも見えます。

神社参道もなかなか急で、見上げて撮影したくなるスポット。撮影:森田季節
さて、テレビが生まれるはるか前から存在したこの巨石は何なんでしょうか。この周囲は竜山石(たつやまいし)という古代から利用されている石の産地です。古墳時代の石棺にも竜山石製のものがあります。この巨石も周辺の石の部分をくりぬいて作ったもので、遠くから運んできたものでも、高所から落ちてきたものでもないです。
奈良時代初期に成立した『播磨国風土記』にはこの立方体の記述がみられるので、奈良時代には「なんだこれ?」と思われていたことは確実です。おそらく、現在まで絶対にこうだという説は出てきておらず、この石が何かは不明のままです。
人生でわざわざ謎のものを見にいくという行為はあまりないと思いますが、たまにはこういう時間の使い方もよいのではないでしょうか。

神社周辺の景観。削られた岩山の痕が生々しく残る。撮影:森田季節
最寄りの宝殿駅から南下していくと、米田(よねだ)天神社という神社があります。こちらは宮本武蔵の養子の伊織が再建した神社で棟札なども現存していますし、武蔵の死後からそう下らない年に神社に奉納された石灯籠なども境内に残っています。おそらく宮本武蔵もこの周囲で生まれた可能性が高いです。周辺は宮本武蔵に関するスポットも点在しているので、生石神社参拝のついでにいかがでしょうか。