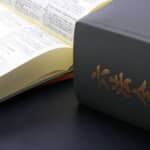朝ドラ『虎に翼』大庭梅子が直面した昭和初期の親権問題 形勢逆転するための制度「監護者」とは?
朝ドラ『虎に翼』外伝⑲
NHK朝の連続テレビ小説『虎に翼』第6週「女の一念、岩をも通す」で、主人公・猪爪寅子(演:伊藤沙莉)は遂に高等試験司法科合格を果たす。しかし、その後ろには世の中の不条理によって夢を断念せざるを得なかった仲間たち、そしてその選択肢を知らなかった女性たちの無念がある。今日はその1人、大庭梅子(演:平岩 紙)の離婚問題と親権について、当時の民法を紐解く。
■愛するわが子の親権がほしい……梅子の母としての切なる願いは叶うのか
大庭梅子は寅子たちの同級生で、唯一の既婚者だった。夫は民事裁判のスペシャリストとして名を馳せる敏腕弁護士の大庭徹男(演:飯田基祐)で、3人の息子がいる母親でもある。
長男・大庭徹太(演:見津 賢)は帝国大学に通うエリートで、父親と同じ弁護士を志している。ところが早くに梅子から取り上げられ、祖母と父の思想に染まった結果、優秀ではあるが母親を含む女性や自分が格下と思う相手を見下す傲慢な人間に育ってしまった。梅子はそのことを深く後悔しており、苦しい胸の内を寅子らに吐露した。
明律大学法学部のハイキングに同行したのは、まだ幼い三男・光三郎(演:石塚陸翔)だ。梅子は次男と三男だけでも真っ当な人間に育ってほしいと願い、弁護士の夫と離婚して親権を獲得する道を模索するために法律を学ぶことを決意したという経緯が明かされている。
ところが、高等試験司法科リベンジ直前、「若い女と再婚するから離婚して出ていけ」と徹男は梅子に離婚届を突き付けた。「息子たちには二度と会えると思うな」という呪いの言葉とともにである。梅子は泣く泣く高等試験司法科受験を断念し、寅子に手紙を出して光三郎を連れて家を出たことを告白した。
■当時の民放に規定された親権と「監護者」
さて、ドラマ内で触れられた通り、当時は民法877條において「子ハ其家ニ在ル父ノ親権ニ服ス」と規定されていた。つまり親権は父親が持つと決まっていたのである。離婚後も当然父親が親権を有するが、事情がある場合は両親の協議を経て母親を「監護者」にすることはできた。これは812條に「協議上ノ離婚ヲ為シタル者カ其協議ヲ以テ子ノ監護ヲ為スヘキ者ヲ定メサリシトキハ其監護ハ父ニ属ス」とある。
残念ながら大庭家はもちろん当時の家制度のもとでは、男女が対等にこれについて協議すること自体がほぼ不可能だったことは言うまでもない。そして仮に協議できたとしても、意見がまとまらなければ問答無用で親権は父親になった。
ほぼ唯一の道として819條「第八百十二条ノ規定ハ裁判上ノ離婚ニ之ヲ準用ス但裁判所ハ子ノ利益ノ為メ其監護ニ付キ之ニ異ナリタル処分ヲ命スルコトヲ得」がある。つまり、812條の規定と異なる判断を裁判所ができると定めたものだ。
言い換えれば、協議以外の手段としてはもはや裁判によって監護者の変更を勝ち取るしかなかったのである。恐らく梅子はここに一縷の望みをかけていたと思われる。ただし、対するは社会的地位を確立している弁護士の夫と帝国大学で法律を学ぶエリート学生の長男という彼女の家庭環境を考えれば、無策で彼らに立ち向かうことは難しく、だからこそ自ら法律を学ぶという道を選んだのだろう。
では父が死亡もしくは行方不明になる、その他何らかの事情がある場合はどうだったかというと、一応母親が二次的親権者として親権を行使することはできた。ただし、重要な財産行為について子を代表したり同意したりする際は、親族一同の同意を得なければならないという制限つきである。
作中ではまだ詳細が描かれていないが、梅子が光三郎を連れて家を出たことに対して徹男らが容認しているはずもない。離婚届を突き付けられた後、離婚が成立したか否かは不明だが、どのような事情があっても現状では“連れ去り”になっている梅子と光三郎のこれからがどのように描かれるのか、親権問題に揺れる令和の世だからこそより視聴者の関心が集まっている。

出典:写真AC
<参考>
■NHKドラマ・ガイド『虎に翼』(NHK出版)
■論説『離婚後の子の貴族―明治民法はなぜ親権と監護を分離したか―』(広井多鶴子)
■『親権法の変遷にみる親権概念―フランス、ドイツ、日本に焦点をあてて―』(德永幸子)