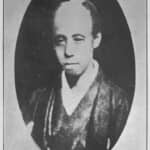徳川吉宗が将軍になれたのは本当にめぐりあわせと運だけだったのか⁉
いま明かされる徳川家の謎
享保元年(1716)、七代将軍徳川家継(とくがわいえつぐ)が亡くなると、次の将軍を誰にするのかが問題となった。強力な候補者がいない中、将軍に選出された吉宗(よしむね)は、あまりにも将軍の座に遠い出自であった。

明治になって描かれた八代将軍徳川吉宗の将軍宣下の様子。三代将軍徳川家光までは京都に上洛して行われていたが、四代将軍徳川家綱からは、絵のように江戸城に天皇の使いである勅使を迎えて行われるようになった。
「観古東錦 舊徳川八代将軍宣下之圖」東京都立中央図書館蔵
15人いる歴代徳川将軍の中で、最も可能性の低いところから将軍になったといえるのが八代将軍徳川吉宗だろう。
徳川幕府を開いた徳川家康(とくがわいえやす)は、子宝に恵まれた人で、男子だけでも11人いた。長男信康(のぶやす)を不幸にして失ったことがあってか、宗家に男子が生まれなかった時のことを考えて、九男徳川義直(よしなお)、十男徳川頼宣(よりのぶ)、十一男徳川頼房(よりふさ)の子孫たちから万が一の場合には将軍候補を出すようにシステムを整えた。この三人の家のことを御三家と呼ぶ。
徳川吉宗は、このうちの徳川頼宣が開いた紀伊徳川家二代光貞(みつさだ)の子として貞享元年(1684)に生まれた。ただし、長男ではなく四男である。この時点で、万が一のことがあっても将軍になれる確率は絶望的に低い。また、結果として九男徳川義直の子孫である尾張徳川からは将軍を輩出することはなかったが、順番としては紀伊よりも尾張の方が先である。
だが、次兄の次郎吉が元服前に亡くなってしまう。徳川吉宗のことを三男と紹介していることもあるのは、この次兄が早く亡くなったため数に入れていないからだ。
当時、家を継ぐ嫡男以外は、部屋住みといい家を継いだ嫡男の扶養家族として肩身の狭い思いをしながら一生を過ごさなければならない。周囲もそれはかわいそうだと思うのか、養子先を探してくる。庶民の場合は奉公先を見つけて家を出ることが多かった。
ところが、吉宗は五代将軍徳川綱吉(つなよし)に目をかけられて元禄十年(1696)14歳の時に、越前国丹生(現福井県福井市、同鯖江市、同越前市の一部)に3万石の領地を与えられた。吉宗の生母の身分が低かったため、兄たちよりも低い扱いを受けていたのを綱吉がかわいそうに思ったからといわれている。しかし、それよりも実は2人とも儒教と蘭学という分野の違いはあれ、学問好きであった。そんなところを綱吉が「見どころがある」と思ったのかもしれない。
部屋住みで終わるかも知らなかったのに、3万石の大名になった。しかし、吉宗の幸運はこれで終わらなかった。なんと、宝永二年(一七〇五)5月、父光貞の跡を継いで三代紀伊藩主となっていた長兄綱教(つなのり)が41歳で亡くなる。彼には男子がいなかったため、弟の頼職(よりもと)が6月に四代紀伊藩主になった。
だが、悲劇はここで終わらない。なんと隠居していた父光貞が8月に、藩主になったばかりの頼職が26歳の若さで身罷(みまか)ってしまったのだ。このため、急遽10月、吉宗は五代目紀伊藩主となり、将軍綱吉から「吉」の字を与えられて、それまでの頼方から吉宗へと名前を改めた。
さらなる幸運が吉宗の元に飛び込んでくる。享保元年(1716)、七代将軍徳川家継が死去。わずか8歳だった家継には子がいない。この時、徳川宗家の血が耐えた。こうした事態に備えて設けられていた尾張、紀伊、水戸の三家からなる御三家の出番である。この時、尾張藩主は徳川継友、紀伊藩主が徳川吉宗、水戸藩主が徳川綱条(つなえだ)であった。
実は、この三人よりも有力な候補がいたのだ、それが徳川継友(つぐとも)の兄吉道(よしみち)である。実は六代将軍家宣(いえのぶ)が亡くなる時に、次の将軍は彼にしたいと名指したのだが、実子の家継がいるからと見送られたことがあったほどの人物であったという。だが、家宣のあとを追うように正徳三年(1713)に亡くなってしまったのだ。また、家宣の実弟松平清武(まつだいらきよたけ)もいたが、すでに54歳と当時としては高齢の上、本人も固辞したため候補から外れてしまった。
有力な候補を欠いたまま、誰を将軍にするかという話し合いが、老中、側用人、家宣の正室天英院の間で持たれた結果、天英院の強い押しがあり、吉宗に決まったという。
こうして、紀伊徳川家の四男として生まれた吉宗が八代将軍の座についたのだが、不思議なことに彼の前に立ちはだかる人々が絶妙なタイミングで亡くなっている。