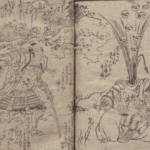差別は消えない。ならば何のために闘うのか──『べらぼう』主人公・蔦屋重三郎が掲げた“目的”と“意味”
『べらぼう』の主人公・蔦屋重三郎はこれまで、いくつもの非常識と思われたことに立ち向かい、打ち破ってきた。どんな相手の懐にもするりと入る持ち前の愛嬌や男ぶりのよさも要因であろうが、不可能を可能にしたのは、何よりもぶれない「目的意識」の高さゆえであろう。第23回では、吉原者への圧倒的差別が蔓延する中、蔦重は日本橋への出店を宣言。「生まれや育ちなんか、人の値打ちとは関わりねぇ」—日本橋出店という無謀とも思える賭けに踏み切れた背景には、心理学者アルフレッド・アドラーの〈目的論〉とヴィクトール・フランクルの〈意味への意志〉に通じる“筋の通し方”があった。蔦重の心の構造を探ってみよう。
■吉原者という逆境を旗印に変える、蔦重の意志力
和泉屋の隠居の弔いに訪れた吉原の旦那衆は、市中の弔問客から侮蔑的な視線を浴び、雨ざらしに遭う。「まぁ、いつものさ」「吉原もんとは、ってやつだよ」—諦観を帯びた、りつらの言葉を聞きながら、蔦重は雨の中で思いを固めた。
日本橋に出店したいという決意を口にすると、養父・駿河屋は激怒する。「誰のおかげでここまでなれたと思ってんだ!」江戸一の利者(ききもの)とまつり上げられ、恩知らずとなったことへの失望、そして我が子を手放す寂しさ。複雑な思いが拳に変わり、蔦重を階段から突き落とす。それでもなお、蔦重は叫ぶ。
「江戸の外れの吉原もんが、日本橋の真ん中で商い切り回しゃ、誰にも蔑まれたりなんかしねぇ。それどころか見上げられまさ。吉原は親もねぇ子を拾ってここまでしてやんだって!……そりゃ、この町に育ててもらった拾い子の、一等でけぇ恩返しになりゃしませんか」
心理学者フロイトは「過去の経験や原因が今を決定づける」という〈原因論〉を打ち出した。いっぽうでアドラーが提唱したのが〈目的論〉だ。「人は過去ではなく、未来の目的によって今を選ぶ」というもので、フロイトの論とは対をなす。
蔦重は過去や生まれを言い訳にせず、未来の自分——「書で世を豊かにする自分」を旗印にして生きるという姿勢を貫いていく。これぞ、目的論の真骨頂である。
蔦重の目的は、平賀源内が名付けた耕書堂の理念「書で日の本を豊かにすること」、そして「吉原を皆が仰ぎ見るところにする」こと。かつて源内と共有した夢こそが、蔦重が進む道の羅針盤であった。田沼父子や大文字屋の抜け荷に与しないのは、己の旗を汚さぬためでもあろう。
さらに須原屋の「おめえに日本橋に出てもらいてえ」という助言で、蔦重の意志は実体を帯びる。吉原者への逆風は強い。だが彼には夢があり、仲間もいる。中でも歌麿が「何がどう転んだって、俺だけは隣にいるから」と語る姿は、アドラーの述べる〈共同体感覚(前回参照)〉を体現しており、アドラーと同時代を生きた精神科医フランクルの〈ロゴセラピー(生きる意味を見出す心理療法)〉の実践そのものだ。
日本ではあまり知られていないが、フランクルもアドラーと同じくオーストリア出身のユダヤ人精神科医だ。第二次世界大戦の折、ナチスの迫害を受けアウシュビッツの強制収容所に収容されるも、奇跡的に生還するという波乱の人生を歩んでいる。フランクルはその時の体験をもとに「どのような絶望的な状況においても、そこに意味を見いだせば人は生きることができる」という考えにたどりついた。これを〈意味への意志〉という。
どんなに「吉原者」と蔑まれようとも、蔦重は書を愛し、書で世を豊かにする夢に生きる。それはユダヤ人として差別され、迫害を受けた過去を持つフランクルの〈意味への意志〉の思想に重なるだろう。
養父の駿河屋をはじめとする吉原の旦那衆たちは、蔦重の思いを受け取り、彼を支援するため結束する。絶望的とも思える逆境にすら意味を持たせ、人生の目的を果たそうとする者の姿は、彼らに関わる全ての人の意識に、大きな影響を与えていくのである。
【まとめ】
差別は消えない。ならば何のために闘うのか—蔦重の答えは、本で世を豊かにし、吉原を“誰もが”見上げる町にするという夢だ。生まれや肩書きを力に変え、人生に意味を見いだし、筋を通して歩む者は、雨上がりの泥道さえ晴れ舞台へ変える。
刻々と価値観が変遷し、たった一度の失敗すら許されない風潮の中にいる私たちこそ、蔦重のゆるぎなき意志力を学ぶべきだろう。自らを振り返り、自らが本当に望む姿を思い出し、旗を掲げ直した瞬間、逆風を追い風にできるかもしれないのだから。

耕書堂(国立国会図書館蔵)