恋人に会いたくて放火の大罪を犯した娘… 無残にも散った「八百屋お七」の恋物語と壮絶な最期
日本史あやしい話
江戸時代に入ってしばらく過ぎた頃のこと、恋人会いたさが募って自宅に火をつけた娘がいた。家が焼ければ、もう一度、恋い焦がれる彼に会うことができるとの一念であった。もちろん、その罪は大きく、極刑を免れることはできるはずもなかった。火付盗賊改役・中山勘解由が温情をかけるも虚しく、刑場の露と消えてしまったのである。いったい、どんな女性だったのだろうか?
■天和の大火で家を追い出された、とある一家の悲劇
「火事と喧嘩は江戸の花」
かつて粋がる江戸っ子たちが、こう言い放ったものであった。もちろん、家事が起きて喜ぶ人など、いるわけもない。ひとたび火が付けば、江戸中が火だるま。多くの人が住処さえ失うことが目に見えていたからである。それでも、江戸を離れるわけにはいかない。「ええい、ままよ!」と、やけっぱちになっての発言だったことが想像できそうだ。
ともあれ、江戸の町は火事が多かった。これは事実である。明暦、明和、文化の大火といった江戸三大大火はもとより、死者100人以上を記録するような火事だけでも、江戸時代の267年間に49回も発生したというから驚くほかない。
天和2(1683)年12月28日に起きた天和の大火も、その一つである。火の手が上がったのは、駒込の大円寺。この時は、北西から吹き荒れる風が災いした。それに煽られて、瞬く間に江戸市中に広がってしまったのだ。死者数、最大3500人というから、何とも悲惨。今回ここで語る、駒込に住むとある八百屋一家が大火で焼き出されたのも、この時のことであった。
もうお分かりだろう。その八百屋の娘・お七が、今回の主人公である。八百屋のお七とは、「恋のために放火したことで、火あぶりに処せられた娘」であることは、多くの方の知るところだろう。ただし、史実としてわかるのは、実はこれだけ。どのような経緯によって放火に及び、さらに火あぶりに処せられなければならなかったのかは、実のところ明確ではないのだ。
それにもかかわらず、この娘にまつわるお話は、細に至るまでよく知られている。それは、彼女の死後、数々の書に記されて、話が膨らまされてきたからである。井原西鶴が著した『好色五人女』も然り、馬場文耕の『近世江戸著聞集』や作者不明の『天和笑委集』などもその一つであった。ここでは、それらに記された、いわゆる物語としてのお七について、今一度、見つめ直してみたいと思うのだ。
■恋のために放火して火あぶりに
舞台は、大火によって焼け出されたお七一家が避難した吉祥寺(正仙院だったとも)である。父が店を立て直すまで、一家が一時的に避難していたところだ。お七が、このお寺に小姓として仕えていた生田庄之助(山田左兵衛だったとも)の見目麗しさに見惚れてしまったのが、運の尽きであった。寝ても覚めても、瞼に浮かぶのは庄之助のことばかり。一方、庄之助の方も、まんざらではなかった。愛嬌深い顔立ちが印象的で、『近世江戸著聞集』によれば、「容貌類いなく美にして、見る人、情を通ぜざるはなかりけり」というほどだったというから、そんな女性から熱き視線を送られて、気にならぬはずがない。彼もまた、心疼くものがあったようだ。となれば、2人が恋仲になるもの、さほど時間はかからなかった。
しかし、お店が建て直され、一家が寺を引き払うことになると、2人は別れ別れにならなければならない。会えないとなると、一層、その想いは募るばかりである。
その隙につけ込んだのが、ならず者の吉三郎であった。2人の恋のキューピット役を演じながらもお七から小遣いをせしめ、挙句、「新居を燃やせば、再び寺で暮らして庄之助と会えるではないか」と焚きつけたのだ。恋に目が眩んで、善悪の判断もつかぬお七。その言に釣られ、とうとう自宅に火をつけてしまった。
この時は幸いにも、すぐに火が消し止められてボヤ程度でおさまったものの、火付けは被害の如何に関わらず、極刑に処せられるのが当時のきまり。お七も、捕縛されて市中引き回しの後、鈴ヶ森において、火あぶりの刑に処せられてしまったのである。
ただし、刑が確定するまでに、取調べに当たった火付盗賊改役の中山勘解由からの温情が取りざたされることもあった。15歳以上なら火あぶりの刑を免れないが、14歳だと嘘でも言い張れば、罪を一等下げてやろうとの思いであった。しかし、これには、お七自身が勘解由の温情を汲み取れず、馬鹿正直にも16歳であると口にしたことで、全てが水の泡。ついには、天和3(1684)年3月28日、衆目が見守る中、うず高く積まれた薪に火をつけられ、その燃え盛る炎の中で、短い生涯を終えたのである。
一方、お七が刑に問われていた頃の庄之助はといえば、長らく病に伏して、お七が死んだことさえ知らなかったといわれる。真相を知った後、出家して彼女の冥福を祈り続けたというが、果たして?
なお、本来なら、重罪人が墓に葬られることはあり得ないと思われるが、文京区円乗寺や鈴鹿森刑場近くの密厳院などに、お七の墓と言い伝えられるところがある。さらには、2人の出会いの発端ともなった駒込の大円寺には、お七と吉三郎(本来は山田佐兵衛のはずであったが、旗本の山田家に配慮して名を吉三郎とすり替えたのではないかといわれる)を共に祀る比翼塚もある。死後とはいえ、2人があの世で再会できたと信じたいものである。

「見立三十六句選」「八百屋お七」
東京都立中央図書館蔵

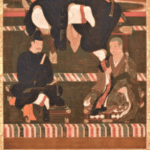



-150x150.jpg)
