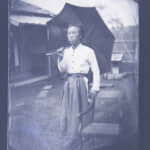江戸の“推し活グッズ”の元祖? 役者絵というジャンルを生み出した浮世絵師・鳥居清信
浮世絵といえば思い浮かべる歌舞伎役者絵。それを生み出したのが鳥居派の鳥居清信で、以後鳥居派と歌舞伎の親密な関係は続く。
■江戸の「推し活」を盛り上げた役者絵
突然だが、皆さんの推しは誰? アイドルや、俳優、スポーツ選手、中には漫画やアニメのキャラクターなどの名を上げる人もいるだろう。こうした推しを応援する推し活グッズの中で一番基本的なのが、カードやポスターではないだろうか。決めポーズの推しとともに毎日生活するというのがファンの醍醐味だろう。この推しのポスター、ルーツは江戸時代までさかのぼることができる。
江戸時代のスターといえば、歌舞伎役者だ。たとえば幕末の人気役者八代目市川團十郎が劇中で浸かった水を売り出したところ若い女性たちを中心に買い求める人が殺到したという。また、彼が若くして謎の死を遂げた後に浮世絵が200点以上も作られたが、どれも飛ぶように売れたという逸話が残っている。
その市川團十郎の初代が出てきたのが元禄時代。初代團十郎は、常識外れのパワーを持ったヒーローを歌舞伎に登場させた。そして悪い奴をバッタバッタとやっつけて人々の心をつかんだのだ。それも派手な化粧を施して日常生活の中では着ないような大げさな衣装で身を包み、飛び跳ねるなどのアクションを取り入れた。いかにも強そうだ。当時の江戸は圧倒的に男性が多い都市だったから、こうしたスーパーヒーローが活躍する荒事と呼ばれる演目が受け入れられたのだろう。
こうしたスーパーヒーローの動きを遠くから見てもわかるように、筋肉を誇張して描く「瓢箪足・蚯蚓描」という技法を編み出したのが、浮世絵師の鳥居清信だった。
鳥居清信は、寛文4年(1664)に大坂で生まれた。父親は女形の歌舞伎役者だったという。幼い頃に京都で絵を学び、父に従って江戸にやって来て芝居小屋の看板を描く仕事に就いた。もっとも父親が役者をやめて看板絵を描くようになり、清信がそれを受け継いだという説もある。当時江戸には幕府から許可を受けた芝居小屋が4つあったが、そのすべての看板を清信が手がけていた。このうち山村座は、正徳4年(1714)に、大奥御年寄絵島と歌舞伎役者生島新五郎が起こしたスキャンダルに巻き込まれて取り潰されてしまった。
芝居小屋の看板は遠くから見ても目立つ必要があったから、必要に迫られて「瓢箪足・蚯蚓描」が生まれたのだろう。この技法が、市川團十郎が得意とする荒事を表現するのにぴったりだったのだ。
鳥居清信は浮世絵のうち、看板絵という肉筆画で世に出たがその後、刷り物の世界へも進出。役者を描いた『風流四方屏風』や吉原の遊女を取り扱った『娼妓画牒』などの絵本を手がけ、人気者となった。絵本で人気が出ると、今度は一枚ものの浮世絵を次々と発表。柔らかい色気のある遊女と、力強い荒事を写し取った役者絵が好評を博した。鳥居清信が、当時の人気役者たちを取り上げた浮世絵を描いて成功したことが、その後数多くの役者絵が作られるきっかけとなったのである。この役者絵こそ、現在作られているスターのポスターの始まりなのだ。
清信は絵を描くだけでなく二代目鳥居清信や鳥居清倍など数多くの弟子を育てた。つい近年まで鳥居派の絵師が歌舞伎座の看板絵を手がけていたのである。

立美人(東京国立博物館蔵 提供colbase)
歌舞伎関係の作品で有名な鳥居清信だが、簡略な線で描いた美人画も数多く残した。勝山髷に結って反故染模様の着物に縞の帯を身に着けた女性の絵は、清信スタイルの完成形とされる代表作である。