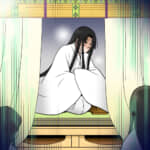【光る君へ】『源氏物語』を愛した菅原孝標女の生涯 1000年の時を越えて今なお読み継がれる物語の魅力
紫式部と平安のヒロインたち#14
主人公・まひろ(藤式部/演:吉高由里子)が書く『源氏物語』は一条天皇(演:塩野瑛久)をはじめ多くの人々の心を掴んだ。そして中宮彰子(演:見上愛)も徐々に自身の気持ちを表に出すようになり、一条天皇との心の距離も縮まっていった結果、遂に2人の間に敦成親王が誕生する。ドラマでは出産時の騒々しい様子が描かれたが、実はこの時の一部始終も紫式部が『紫式部日記』に記していた。
■『源氏物語』を愛した菅原孝標女

イラスト/関根 尚
大河ドラマ「光る君へ」の最終回に、菅原孝標女(すがわらのたかすえのむすめ)が登場しました。菅原孝標女は『更級日記』の作者として有名です。文学史を考える上でも、孝標女の登場は、とても象徴的で、喩えていえば、バトンの継承が暗示された、見事な演出だったと思います。
菅原孝標女は寛弘5年(1008)に生まれました。その年は、藤原公任が紫式部に向かって「あなかしこ、このわたりに若紫やさぶらふ」(畏れ多いことですが、このあたりに若紫は控えていますか)と声をかけた年でした。宮中で『源氏物語』が、今で言うベストセラーになった年に奇しくも孝標女は生を受けたのです。現在の千葉県市原市で、父孝標の上総介赴任に伴って10歳から13歳までの多感な時期を過ごした孝標女は、継母や姉の語る『源氏物語』の断片的なストーリーに魅了され、早く上京して、『源氏物語』を入手して読んでみたいと願うのでした。
当時の物語は、書写することによって広まっていきました。現代の本の流通と異なり、書店やネットで注文すれば手に入るというものではありません。孝標女は姉や継母の語る断片的なストーリーで『源氏物語』を知ったというのですから、東国にいた孝標女の許には、物語の写本はなかったのです。むしろ、そのような都から遠く離れた地で、この物語が女性たちの話題になっていたことに驚くべきでしょう。
実際、上京後も孝標女は『源氏物語』の入手に苦戦しました。最初に一部の巻を手に入れて読んだ孝標女ですが、そこは大長編の物語ですから、なかなか全巻入手するにはいたりません。しかし、母に事あるごとに物語の入手をせがんだ結果、上京してきた「おば」(伯母か叔母か不明です)から五十余巻の『源氏物語』を手に入れることができたのです。五十余巻という言い方は微妙ですが、コンプリートに近いものだったのでしょう。孝標女は、几帳の内に臥して夢中になって読み耽るのでした。その気持ちは「后の位も問題にならないほど幸せだった」と記すほど、濃密な、陶酔の時間でした。そして、自分が将来、もっと女盛りになって髪が長くなったら、夕顔や浮舟の女君のようになれるのではないか、と14歳の孝標女は夢想するのです。
なぜ夕顔と浮舟だったのか。比較的、孝標女に近い身分だったから親近感があったとする説(実際には、夕顔は三位中将という高官の娘でしたが)や悲劇的なキャラクターが少女の共感を得やすかったとする見方もあります。それはそれとして、それだけ『源氏物語』の登場人物は、少女の将来のモデル像になるほど、リアリティがあったのでしょう。『源氏物語』の登場人物たち、特に女性たちは、いずれも個性的で、現代の私たちでもイメージが湧きやすい存在です。紫の上、葵の上、六条御息所、明石の君、末摘花と女君の名を挙げていくだけで、『源氏物語』の愛読者は、それぞれのキャラクターが頭の中に浮かんでくるのではないでしょうか。現代でも、たまにイエス、ノーで、チャートを答えていくと、あなたはこの女君のタイプだよ、というような雑誌の記事を見かけることがありますが、それだけ『源氏物語』のキャラクターは個性的で、現代の我々にも身近に感じられる、普遍性を持っているのでしょう。
話が逸れたようですが、紫式部が仕えていた宮中にいた女房たちも大変個性的です。打てば響く、ウィットに富んだ清少納言、恋多き情熱の歌人である和泉式部、良妻賢母でしっかり者の赤染衛門など、キャッチフレーズとともに呼べるような個性が紫式部の同時代の女房たちにはあったのです。このような個性を発揮しつつ、和歌を詠み、物語を書き、日記を記すことがお仕えする主人の名声を高めることにつながったのです。そのような幸せな時代に『源氏物語』は作られました。その登場する女性たちの個性は、同じ時代の女房たちの個性と響きあう関係にあるように思うのです。紫式部一人が傑出した天才ではなく、その天才を発揮できる環境があったのです。
もちろん、集団生活の中で、「出る杭は打たれる」を地で行くように、その傑出した才への嫉妬が生まれ、周囲に多少の軋轢があったでしょうが。
さて、『更級日記』は藤原定家が写した写本が現在まで伝えられていますが、その写本の終わり近くに、仮名で書かれた奥書があります。それに拠ると、孝標女は『夜の寝覚』や『浜松中納言物語』などの長編物語の作者であると伝えられていたのです。この伝承が正しいとすると、孝標女は物語を創作していたことになります。近年の研究の深まりは孝標女が物語作家であったことを追認する方向にあり、特に『浜松中納言物語』の作者は『更級日記』との類似性から孝標女と考えて良いでしょう。孝標女は『源氏物語』の熱狂的な読者から物語作者に転身していたのです。
『更級日記』に拠ると、孝標女は39歳のとき、初瀬(長谷寺)に向かう途中に、宇治に立ち寄っています。宇治は『源氏物語』宇治十帖の舞台です。宇治川沿いの風光明媚な場所でした。そこで、孝標女は次のように書いています。
紫の物語(『源氏物語』)に、宇治の八の宮の娘たちのことが書かれているが、どのような所だから、そこに住ませたのだろうと知りたいと思っていたのだった。なるほどすばらしい所だなあと思いながら、やっと宇治川を渡って、関白頼通さまの御領所に入って、浮舟の女君はこのような所に倒れ伏していたのだなあと、まず思い出されたことであった。
孝標女は今で言う聖地巡礼のような思いで、宇治の地を訪れていたのでしょう。後に平等院となる頼通の別邸を訪れ、入水を図り宇治川の岸で倒れていた浮舟の姿を現実の光景の中で重ね見ていたのではないでしょうか(私はここまで踏み込んで解釈すべきだと考えています)。さらに注目したいのは、宇治の八の宮の娘たち、大君、中君がなぜ、そこで成長したように書かれたのかという物語の構想上の問題に言及していることです。原文には「いかなる所なれば、そこに住ませたるならむ」とあります。ここでの主語を父である八の宮とし、娘たちを住ませたと解する説もありますが、八宮は都から逃れるように、この地に来たので、娘たちを育てる場所の選択の余地はなかったのです。主語は『源氏物語』の作者である紫式部と考えるのが自然です。そうだとすれば、ここで孝標女は物語作者である紫式部の創作意図に言及し、思いを馳せていることになります。孝標女は宇治の地を訪れて、なぜ大君と中君がこの地で育ったように書いたのか、紫式部の意図をなるほどと実感したのです。ここに、紫式部から孝標女へと物語作者の系譜が脈々と息づいていることを感じます。
『源氏物語』は光源氏が藤壺の代わりに血縁があり、似ている紫の上を愛したように、「形代」の論理が物語を大きく動かしました。孝標女は『浜松中納言物語』で「形代」に代わり、「転生」の論理を物語に導入し、唐と日本を魂が往還する物語を創造しました。それは偉大な『源氏物語』に対する、孝標女の挑戦でした。
紫式部は同時代の人々だけではなく、後代の人々を魅了し、影響を与え続けました。大河ドラマは終わりましたが、これからも紫式部の文学は新しい読者たちを獲得し、時空を越えて人々の心を駆り立て続けることでしょう。
<参考文献>
福家俊幸『紫式部 女房たちの宮廷生活』(平凡社新書)
福家俊幸『更級日記全注釈』(KADOKAWA)