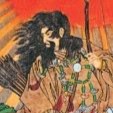そもそも古代の有力氏族「蘇我氏」というはものは存在しなかった!?
敗者の日本史

蘇我入鹿
■馬子や蝦夷の時代には、まだ氏族は存在しなかった?
日本古代に氏族が登場するのは天智朝になってからであろう。そもそも5世紀後半の稲荷山(いなりやま)鉄剣の銘文には「乎護居臣」などと「氏(うじ)」名なしで名前だけが記されている。「名前+ 姓(かばね)」である。それゆえ八色(やくさ)の姓の制定が必要だったのであり、氏の整理は必要なかったのではなかろうか。天武13年(684)10月に定められた「八色の姓」は、「諸氏の族姓(かばね)を改めて、八色の姓を作りて、天下の万姓(よろづのかばね)を混(まろか)す」とある。「諸氏」とあることから、すでに天武朝に氏族がいたような印象を受けるが、一般的に諸氏がこの時点で存在したとは思えない。天智八年十月庚申条に天智が鎌足(かまたり)に「大織冠と大臣の位を授く。仍(よ)りて姓(うじ)を賜ひて、藤原氏とす」とあり、それ以前から「藤原内大臣」と書かれている鎌足に対して新たに「藤原」の氏を賜ったという記事がある。これも唐の羈縻(きび)支配をうけた影響ではなかろうか(拙書『天智朝と東アジア』NHKブックス)。中国では「氏」は重視されていた。
そもそも「氏」はすべての人々が持つものではなかった。大王家が後々まで氏を持たないのはその名残であり、尊敬の意味ではない。もし無姓が尊敬されているのならば、庶民は無姓だから、同じく尊敬されていたといえるであろうか。
■馬子や蝦夷が使用した〝蘇我〟以外の名称
蘇我(そが)を冠する人々も、蘇我の地に住むことが第一条件で、地縁的結合といえよう。血縁的結合原理ではない。たとえば、蘇我馬子(うまこ)が推古三十二年十月朔日条に「葛城県(かづらきのあがた)は、元臣(もとやつかれ)が本居(うぶすな)なり、故(かれ)、其の県に因(よ)りて姓(うじな)名を為(な)せり」と述べている。つまり馬子は葛城馬子と称したというのである。これも蘇我や葛城が氏名ではなく、居住地でしかないことの証明であろう。また蘇我蝦夷(えみし)は舒明八年七月朔日に「豊浦大臣(とゆらのおほおみ)」と表現されている。豊浦の地は飛鳥寺から西北にあたる地である。おそらく蝦夷はここに居住したから「豊浦」大臣と称されたのであろう。もし「蘇我」が氏(うじ)名として定着していたならば、別称は成り立ちにくい。
さらに皇極二年十月壬子条に、入鹿(いるか)の弟を指して、「復其(またそ)の弟(おと)を呼びて、物部大臣と曰ふ。大臣の祖母(おば)は、物部弓削大連(ゆげのおおむらじ)の妹(いも)なり」とある。これなども、蘇我や物部が氏名でないことの証左であろう。入鹿にしても弟にしても、「蘇我氏」という氏族が確立しているならば「物部大臣」と呼ぶことはないであろう。『日本書紀』が「蘇我+名前」や「物部+名前」の表記をしているのは、氏族が一般化してからの知識による潤色と考えるべきではないであろうか。
監修・執筆/中村修也