大河ドラマ『光る君へ』中宮定子の母・高階貴子 栄華を極めた才女の悲劇的な最期とは
紫式部と平安のヒロインたち#03
大河ドラマ『光る君へ』ではいよいよ一条帝(演:塩野瑛久)の御代になり、摂政・藤原道隆(演:井浦新)が政治を思うままに動かす、中関白家の絶頂期を迎えている。一条帝の寵愛する中宮定子(演:高畑充希)の豊かな教養と賑やかなサロンの様子は『枕草子』でも詳細に綴られているが、その背景には定子の母であり道隆の妻である高階貴子(演:板谷由夏)の存在があった。その才によって最高の幸せを手にした女性の一生をご紹介する。
■漢詩・漢文の才で自らの人生を切り拓いた女性
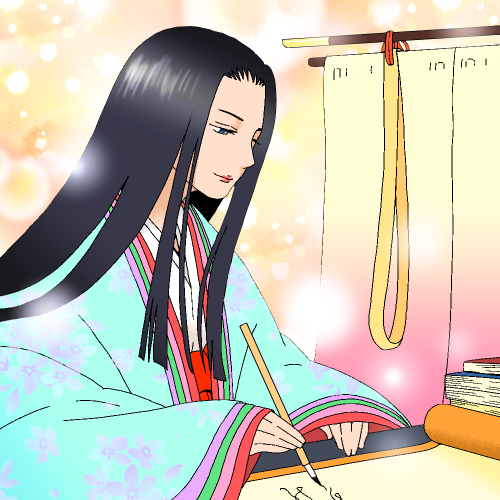
イラスト/関根尚
高階貴子は藤原道隆の正室で、伊周(これちか)、定子、隆家らの母でした。高階家は中流貴族の家柄でしたが、貴子の父・高階成忠は学才に優れた人物でした。
そもそも高階貴子は高内侍(こうのないし)という女房名で知られた、宮仕え女房でした。『大鏡』という歴史物語は貴子について次のように記しています。「高内侍(高階貴子)は本格的な漢詩人で、天皇の御前で行われる作文会(漢詩を作る会)に参加し、漢詩を作ったということだ。いい加減な男よりもよほど優れているという評判だった」(道隆伝)。
同じく歴史物語の『栄花物語』は「円融院の時代に、貴子を宮仕えに出させたところ、女ではあるが、漢字をたいそうよく書いたので、内侍(天皇付きの女房)になさって、高内侍といわれるようになった」(さまざまのよろこび巻)と伝えています。高内侍は何よりも男性顔負けの、漢籍の素養で有名な女房だったのです。
そのような才女と道隆は、現代の職場恋愛のような形で結ばれたようです。『栄花物語』は子供たちが優れていたのは、この北の方の才知のおかげだと記しています。
貴子の子供たちが漢文の才を発揮したのも、母の薫陶の賜物だったのでしょう。長男伊周は漢詩人としても有名でした。
同じく貴子の娘であった、一条天皇の中宮(皇后)定子も漢文の教養がありました。『枕草子』の有名なエピソードである、定子が「少納言よ。香炉峰(こうろほう)の雪いかならむ」と尋ねたのに対して、清少納言が格子を上げさせて、簾を巻き上げたのも、元ネタである白居易(白楽天)の漢詩を定子も清少納言もよく知っていたことから成り立つパフォーマンスでした。『枕草子』には漢文の教養を元に清少納言が男性貴公子達と丁々発止と渡り合う様子が描かれていますが、このような清少納言の活躍は定子のサロンが漢文の教養を積極的に発揮することができる環境であったことを示してもいます。
この時代、女性が漢文の知識を人前で示すのを白眼視する見方が根強くありました。『紫式部日記』には、紫式部が漢籍を読んでいると、侍女たちが「だから、おかた様は幸薄いんだ」と陰口を言うと記しています。定子のサロンは開明的な環境だったのです。そこには、若き日、漢詩を作って評判となった高階貴子の影響があったのでしょう。貴子の存在は、定子のサロンの持つ新しさ、伸びやかな明るさにも繋がっていたのではないでしょうか。
将来を嘱望された貴公子伊周や一条天皇の寵愛をほしいままにしていた定子。そのような子供達に囲まれた貴子ですが、夫道隆の急逝、さらに伊周が弟隆家とともに、花山院を矢で射かける不祥事を起こしたことなどから運命が変転します。伊周・隆家はそれぞれ太宰権帥、出雲権守に落とされ、流罪が決まります。心労もあったのでしょう、重病に倒れた貴子は伊周と一目会いたいと念願し、その母の思いに引かれ、伊周は一旦据え置かれた播磨国から密かに入京します。
定子も加わり、涙ながらに会う場面は『栄花物語』浦々の別巻に感動的に描かれています。「今はもう安心して死ねる」と貴子は喜ぶのでした。この後、密告する者がいて、伊周は逮捕され、九州の大宰府に流されました。貴子は息子達の召喚を待つことなく、間もなく亡くなりました。
『大鏡』は貴子について、次のように記しています。「女が学才の優れているのはよくないと世間の人々が申しているが、(後に)この高内侍がたいそう零落されたのも、そのためだったと思われた」(道隆伝)
この記述は、女性が漢詩・漢文に優れていることをネガティブに受け止める、保守的な見方が強く存在していたことを示しています。それだけ高階貴子は時代に先駆けた女性であったと言えるかもしれません。
<参考文献>
福家俊幸『紫式部 女房たちの宮廷生活』(平凡社新書)






