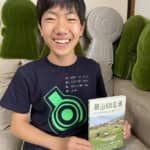【偉人クイズ】関ヶ原の戦いで負けた宇喜多秀家。島流しにされて何歳まで生きた?
偉人クイズ
突然ですが、歴史クイズの時間です!親子で楽しく問題を出し合いながら遊んでみてね!【歴史人Kids】

八丈島に所在する宇喜多秀家の像
秀吉がつくった豊臣(とよとみ)政権で、五大老(ごたいろう)のひとりとして活躍した武将が宇喜多秀家(うきた ひでいえ)です。
秀家は策略家(さくりゃくか)として知られた備前(岡山県)の戦国大名・宇喜多直家(なおいえ)の次男として生まれました。しかし、秀家がまだ10歳のとき、父が亡くなり、家督(かとく)を継ぐことになったのです。
それまでは「八郎(はちろう)」とか「家氏(いえうじ)」と名乗っていましたが、秀吉から「秀」の字を与えられ「秀家」と名乗ります。その後、秀吉の養女・豪姫(ごうひめ)を妻にむかえ、秀吉の一門衆(いちもんしゅう=身内)として大切にあつかわれました。
そして1595年、五大老に任命されたのですが、徳川家康54歳、前田利家57歳、毛利輝元43歳、上杉景勝40歳という、そうそうたるメンバーのなかで、もちろん秀家はいちばん年下の24歳。そんな彼が五大老になったのは、秀吉の身内だったからです。
そんな秀家ですが、慶長5年(1600)関ヶ原の戦いのときがやってきます。諸説ありますが、西軍主力の中でも、最大の兵力(一説に1万7000人)を率いて参戦。戦場では猛将・福島正則(ふくしま まさのり)隊などと懸命(けんめい)に戦いました。しかし、ごぞんじのように西軍は敗れます。秀家は、薩摩(さつま)の島津(しまづ)家を頼って九州へ逃げていきました。
しかし、それはやがて徳川家康の耳に届きました。本来は打ち首となるはずでしたが、島津氏や前田氏などのような有力大名のとりなしで、伊豆の八丈島(はちじょうじま)へ流されるという刑がくだりました。このとき慶長11年(1606)、35歳でした。
それから50年近くもの間、秀家は罪人としてあつかわれたまま、この島で過ごしました。しかし、まだ若く聡明な秀家をほうっておけず、妻の実家の前田家や旧家臣から生活に必要な物資(ぶっし)が送られ、ほかの流人(るにん)より良い暮らしをしていたそうです。
嵐のため島に退避した福島正則の船に酒を恵んでもらったり、代官に、おにぎりをご馳走になったという逸話もあります。
島では、ともに流罪となった息子や家臣たちとの共同生活でした。
けっきょく、秀家は関ヶ原に参戦した武将のなかでは一番ながく生き、明暦元年(1655)に84歳の生涯をしずかに閉じたのでした。