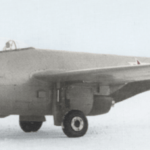史上唯一の実用ロケット戦闘機【メッサーシュミットMe163コメート】
ジェットの魁~第1世代ジェット戦闘機の足跡~ 【第22回】
ジェット・エンジンの研究と開発は1930年代初頭から本格化し、1940年代半ばの第二次世界大戦末期には、「第1世代」と称されるジェット戦闘機が実戦に参加していた。この世代のジェット戦闘機の簡単な定義は「1950年代までに開発された亜音速の機体」。本シリーズでは、ジェット戦闘機の魁となったこれらの機体を俯瞰(ふかん)してゆく。

メッサーシュミットMe163コメート。胴体下の大きな主輪は機体重量軽減のため離陸直後に投棄される。そして帰還時は、写真でも見えるソリを使って着陸滑走をした。大型の重爆撃機を迎撃するので、強力な30mm機関砲2門を装備していた。
今回は、ジェット・エンジンではなくロケット・エンジンを搭載するロケット戦闘機を紹介したい。というのも、現在のところ本機が史上唯一の実用ロケット戦闘機なので、独立したジャンルで語れないのと、初期のジェット戦闘機と同時期に開発された機体だからだ。
動力機関研究者のヘルムート・ヴァルターが開発したヴァルター液体燃料ロケット・エンジンは、外部から空気を取り入れることなく、高濃度の過酸化水素水(T液)にヒドラジンとメチルアルコールの混合液(C液)を混ぜることで生じた化学反応で推進力を得る。
このロケット・エンジンと、グライダーの研究では世界最先端ともいえるアレキサンダー・リピッシュが設計した無尾翼の機体を組み合わせて、ロケット戦闘機が開発された。
メッサーシュミットMe163コメート(「流星」の意)と命名されたこの機体は、ロケット・エンジン始動後は急速に高速飛行が実施できるが、同エンジンの作動時間が短いので高速飛行時間も短く、したがって交戦も短時間しかできなかった。そこでドイツ空軍は、ドイツ本土爆撃に飛来する重爆撃機の迎撃に用いる計画を立案した。
しかし増加試作機を実戦で運用してみると、毒性がきわめて強い燃料液の取り扱いや貯蔵、そして輸送がいずれも困難で、離陸に際しては強力なロケット噴射に耐えられる堅牢な滑走路が必要なうえ、飛行時間が極端に短く、航続距離も短いので戦闘のために離陸するタイミングを掴むのが難しいだけでなく、きわめて短い航続距離内に敵機が侵入してこなければ、出撃しても交戦できなかった。
おまけに動力飛行終了後の帰還時は、単なる滑空グライダーにすぎないため、連合軍の戦闘機の恰好の餌食になりかねなかった。
このように、ロケット戦闘機の運用にはきわめてデリケートなオペレーションが必要な割に、効果は乏しかった。それでもMe163は約350~400機ほどが生産され、実戦で敵機9機を撃墜(異説あり)したとも伝えられる。