吉原の魅力を記した『吉原細見』の歴史
蔦重をめぐる人物とキーワード③
■吉原出身の蔦重の才覚が発揮された案内本
吉原遊郭のガイドブックの役割を果たす『吉原細見(よしわらさいけん)』は、江戸中期以降に広く出版されるようになった。
『吉原細見』の登場以前は、『遊女評判記』がその役割を担っていたという。『遊女評判記』はその名の通り、遊女の評判をまとめたもので、人気の遊女の外見や性格を紹介するのが主な内容だったようだ。そのほか、遊女にまつわる噂話や遊郭での遊び方の指南といった情報も織り交ぜられており、いわば読み物が中心の存在だったらしい。
一方、『吉原細見』は郭内のマップを掲載し、どこに遊女屋があるのか、そこに所属する遊女、あるいは茶屋の紹介、遊女の揚代を明記するなどの特徴がある。遊女はもとより、遊郭全体を網羅して紹介する情報誌のような色合いだった。
『吉原細見』の最も古いものは、貞享年間(1684〜1688年)のものという説がある。当初は一枚刷りで吉原の地図が掲載されたものだったが、やがて横本の形に統一。享保年間の中期に当たる1725年頃には、かなりの点数が発行されたという。
人気の冊子だったため、版元もこぞって乗り出したようで、出版したのは鱗形屋孫兵衛、相模屋与兵衛、鶴屋喜右衛門、相模屋平介、三文字屋亦四郎、山本九左衛門といった版元が記録に残っている。ところが、1738(元文3)年頃には、『吉原細見』を刊行する版元は鱗形屋と山本九左衛門しか残っていなかったらしい。
両版元は、新旧の遊女を誌面に反映するべく春と秋の年二回発行に統一している。1758(宝暦8)年に山本九左衛門が撤退したことで、事実上、『吉原細見』発行は鱗形屋のほぼ独占状態となった。
当時、出版といえば上方(京都や大坂)が中心で、江戸では上方で流行りの書物を販売することが多かったようだ。
山本九左衛門はそもそも上方の版元で、江戸の店舗は支店のような形であったのに対し、鱗形屋は出版物こそ上方のものを取り扱うことから始めたものの、江戸で生まれた版元だったので、こうした地の利が影響したのかもしれない。いずれにせよ、『吉原細見』の独占販売だけでなく、江戸発祥の文学にも力を入れていたことから、鱗形屋は江戸を代表する老舗の版元として、確固たる地位を築いていった。
前述したように、初期の『吉原細見』は一枚刷りで吉原の地図が掲載されたものだった。そこには遊女屋や所属する遊女の名が記載されるなど、のちの細見の原型となったが、一枚刷りといってもかなり大きなものだったようだ。折りたためば携帯するのに苦労しないが、広げると両手いっぱいに広がるサイズで、いちいち広げてはたたみ、たたんでは広げ、などしていては、吉原見物もままならなかったに違いない。
そこで、1727(享保12)年に横本の細見が登場した。掲載する情報は一枚刷りと同じ内容だったが、サイズがコンパクトになり、携帯性が高まった。そうした狙いは、伊勢屋という版元の細見に、見やすいように懐中本に改めた、とする記述があることからも明らかだ。
横本形式に改良を加えたのが、蔦屋重三郎だ。蔦重は、横本から縦本に改めている。大きさこそ横本より一回り大きくなったものの、通りを挟んだ遊女屋を上下に配置して1ページにおさめるなど、分かりやすいデザインを用いて、視認性を高めた。横本に比べて1ページに収められる情報量が増えた一方、ページ数をおさえて制作費用の削減にも成功していたようだ。
また、吉原に生まれ育った蔦重ならではの情報網を使って、入れ替わりの激しい遊女の名前を正確に記し、遊女のランクが分かるよう表示。揚代(利用するための料金)を明確にしたり、吉原で行われる年中行事をまとめたりするなど、吉原を利用する人々にとってかゆいところまで手が届く内容に改良が重ねられた。
さらに、一流の文化人による序文を掲載することでブランド力を高めた蔦重版『吉原細見』は、またたく間に人気となった。以降、蔦重の『吉原細見』の形式は定着し、明治に至るまで発行され続けたという。
なお、劇中で描かれた『一目千本』は遊女評判記の一種で、蔦重が出版業に参入して初めての書籍として知られている。
- 1
- 2



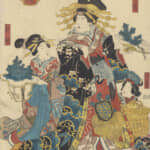
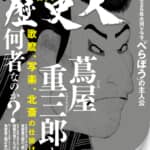
_電子透かしあり-150x150.jpg)
