清少納言は「身分の低い人」を見下していた!? 今なら大炎上する『枕草子』のヤバい発言
日本史あやしい話48
大河ドラマ「光る君へ」ではファーストサマーウイカ氏が好演している清少納言。彼女が著した『枕草子』には、身分の低い者を卑下するような記述が満ちあふれている。敬愛する定子に対しては、心憎いばかりの気遣いを見せていた一方で、かなりの毒舌家だったのである。どんな発言をしていたか、見てみよう。
■「貧乏人の家は風流じゃない」「月明かりももったいない」
.jpg)
清少納言(ColBase)
清少納言とは、なんとも「嫌な女」である。かの紫式部が日記の中に、「したり顔にいみじう侍りける人」(得意顔をして偉そうにしている)と記したことは、誰もが知るところだろう。
そのときの紫式部に多少の嫉妬心があったことは間違いないだろうが、思いのほか、正しい評価であったと、筆者は密かに頷いている。清少納言の著作『枕草子』を見て、同じような思いに駆られた人も、少なくないのではないだろうか。彼女の毒舌ぶりが、そこかしこに際立っているからだ。
一例を挙げてみよう。まずは第42段から。そこに記された主題は「似げなきもの」(似合わないもの)であるが、その代表格としてあげられたのが、「下種の家に 雪の降りたる」というものであった。
「下種の家」とは、身分の低い人の家の意。つまり、卑しい身分の貧しげなる家に雪が降り積もるなど、風流でも何でもないから、似つかわしくない。美しい雪景色は、身分の高い者の大邸宅に降ってこそ似合うものだと言うわけである。
たしかに、豪奢な邸宅に降り積もる雪景色こそ綺麗なのかもしれないが……。続けて、「また 月のさし入りたるも 口惜し」とも。月明かりの美しさまで、貧しい人には見る価値もないかのような言い草なのだ。
■「痩せた色黒い人に生絹の衣は似合わない」
第91段の「かたはらいたきもの」(どうにも我慢ならぬもの)では、「旅だちたるところにて 下種どもの戯れゐたる」との一文が登場する。旅先などで羽目をはずすことは、高貴な身分の者なら許せるが、下賤の者が騒ぎ立てるなど我慢ならぬという。
貧しい者への嫌悪に満ち溢れた言葉はまだまだある。第134段では、「取りどころなきもの」(取り柄のないもの)として、「痩せ 色黒き人の 生絹の単衣着たる いと見苦しかし」と記している。
ふくよかで色の白い女性が薄くて上品な生絹の衣を着るのは良いが、やせ細った色黒の女が身にまとうのは、薄汚くて貧相だということか。見栄えの悪い人間は、まるで生きている価値もないかのような言い方である。
そればかりか、大して可愛くもない子を赤ちゃん言葉であやす母親さえ、「かたはらいたきもの」(我慢のならないもの)(第91段)とまで言い切る始末。
もちろん、「春はあけぼのようよう白くなりゆく山ぎは すこしあかりて〜」から始まる冒頭の一節を始め、四季折々の美しい情景を感性豊かに歌い上げたその才能には敬意を評したいが、身分や見栄えの良し悪しにまつわる毒舌は、なかなかに強烈である。

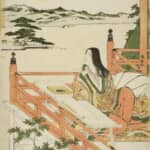


-e1704957789649-150x150.jpg)
-150x150.jpg)
