紫式部は恋愛上手だったのか? 光源氏に似た「インテリ貴公子」との関係とは
日本史あやしい話41
大河ドラマ「光る君へ」で注目を集めている紫式部。彼女が書いた『源氏物語』とは、イケメン貴公子が女たちをつぎつぎと口説き落としていく恋愛小説である。男女の機微を入念に描いているところから見ると、紫式部が恋に疎い女性だったとは思いにくい。実際のところ、どのような恋をしてきたのだろうか?
■紫式部の恋愛遍歴
『源氏物語』といえば、手っ取り早く言えば、イケメン貴公子に突如言い寄られて、拒む間もなくその手に抱かれていく…といった、ハレンチ極まりない出来事を連綿と書きつづった小説である。
この物語が男女の機微を入念に描いているところからすると、作者である紫式部自身が、男女問題に関して、思いのほか熟達者であったようにも思える。一見、人見知りで堅物と思われがちな紫式部ではあるが、実は経験豊富なのではないだろうか?
ただ残念なことに、彼女が998年ごろに藤原宣孝と結婚したという以外、男性遍歴に関しての情報はほとんどない。紀貫之の子・時文との関係が取りざたされたほかは、めぼしいものといえば、『紫式部集』に記された「方違えで紫式部宅を訪れた男が、姉妹で寝ていた床に潜り込んできた」ことぐらいか。
また、未亡人となった後は、誰かは不明ながらも、求婚者が現れたらしい。さらには、彰子入内と前後して、時の権力者・道長との関係が噂されたこともあったが、こちらは未だ真偽のほどは不明である。
ともあれ、記録には残されてはいないものの、残された和歌などを読み解きながら、推理してみたい。
■和歌に示された「初恋の相手」
少女時代の恋バナに関しては、参考になるような情報は手に入らないが、彼女が父とともに越前(武生)へと出立していったあたりから、少しずつ関連する和歌が残されていくので、それらを参考にすることにしたい。
まず気になるのが、下記の『紫式部集』に収められた歌である。
「また 磯の浜に 鶴の声々に鳴くを 磯がくれ おなじ心に 鶴ぞ鳴く 汝が思ひ出づる 人や誰ぞも」
紫式部が琵琶湖に立ち寄った際、漁師が網を引く姿を見て詠んだ歌である。筆者なりに読み解いてみれば、「磯浜で鶴が切なそうに鳴くのは、今の私の気持ちと同じ。いったい誰を思い出して泣いているのかしら」といったあたりだろうか。
ここに記された、紫式部自身が切なく思う「思ひ出づる人」が誰だったのか、これがなんとも気になる。越前行きにあたって、彼女に「恋しく思う人がいた」ということを物語っているからだ。
■藤原宣孝はオジサンすぎる?
ここで誰もが、いの一番に思い付くのが、のちに夫となる藤原宣孝なのかもしれない。ただし、これは彼女の性格からして、あり得そうもない。
彼は『枕草子』にも記されたように、派手好きの伊達男だったことは間違いないが、歳は紫式部より20歳近くも上。
父親にも近いようなオジサンであるばかりか、地位も父と似たり寄ったりの従五位上(後に正五位下)の受領階級である。『源氏物語』であれほどイケメン貴公子を賞賛し続けた作者としては、とても憧れるような対象ではなかったと思われるからだ。
では、紫式部がこのとき、心に思い描いていた「思い人」は誰か? ズバリ、それは、村上天皇の第七皇子・具平親王だと見なす識者が少なくない。ここでは、その可能性について、あらためて考えてみることにしたい。
■身の程をわきまえて宣孝と結婚
.jpg)
時代異歌合絵断簡(中務卿具平親王・愚詠)
なぜ、具平親王が紫式部の「思い人」だったと推測できるのか? 実のところ、明確な記録は見当たらない。それでも、『源氏物語』の主人公・光源氏を彼女が抱く憧れの男性像だと仮定すれば、それに符合するのが具平親王しか見当たらないのである。
まず、皇族に連なる貴種であるというのが第一条件である。親王は帝の子だから文句なし。さらに、詩歌や書に優れた文人としても尊敬できる御仁である。プライドの高い紫式部としては、これらの条件を満たさなければ、憧れの対象とはならなかったに違いない。
ただし、現実を振り返ってみれば、我が身は受領クラスの娘。仮に親王と結ばれたとしても、とても正室として迎え入れられるはずもない。想いを断ち切るために、さして興味も湧かない越前行きに同意したのだろう。そこで暮らすこと1年半。
心の傷が少し癒えたところで、身の程をわきまえたと言うべきか、歳の離れた宣孝からの申し出を渋々了承して、都へと戻っていったのではないか。そんな風に、想像を逞しくしてしまうのである。
さらに、具平親王との関係は、藤原道長の「思惑」にも関わるように思える。
- 1
- 2

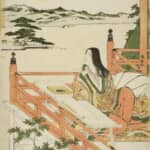


-e1704957789649-150x150.jpg)
-150x150.jpg)
