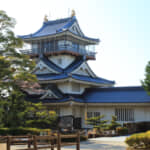秀吉への「絶対服従」の誓紙に署名していた家康
史記から読む徳川家康㊱
翌月の15日に、秀吉は諸大名に誓紙の提出を求めた(「大友家文書録」)。主な目的は、秀吉に対して絶対の服従を誓わせるもので、家康は織田信雄(おだのぶかつ)、秀長、豊臣秀次(ひでつぐ)、宇喜多秀家(うきたひでいえ)、前田利家(まえだとしいえ)との連署という形で提出している(『聚楽亭行幸記』)。
家康が駿府に戻ったのは同月27日のことだが、この頃から、秀吉
同年5月21日、家康は北条父子に対して、上洛と秀吉への臣従を催促すべく、起請文を送った。今月中に兄弟衆を上洛させなければ、嫁に出した娘の督姫(とくひめ)を返すよう迫る内容だった(「鰐淵寺文書」)。同盟破棄をも匂わせる強い態度に、北条氏もようやく重い腰を上げることになった。
そんななか、秀吉の母である大政所(おおまんどころ)が病気を患ったとの知らせを受けた家康の正室・旭姫(あさひひめ)は見舞いのために上洛。同年6月22日のことだった。家康も少し遅れて、旭姫の後を追って上洛している(『家忠日記』)。
同年8月22日、再三の家康の催促を受けて北条氏規が上洛。聚楽第で秀吉に謁見した(『北条五代記』『多聞院日記』『家忠日記』)。この時、秀吉は北条氏に従属する意思があることを認めた。さらに、懸案の沼田領の帰属問題について踏み込んだ裁定をしている。内容は、沼田領を分割し、北条氏と真田氏にそれぞれ所領として与える、というものだった(「真田家文書」)。
翌1589(天正17)年2月13日、家康と真田昌幸との間で講和が成立し、長男の信幸が家康のもとに送られている(『家忠日記』『信州松代真田家譜』)。
同年5月19日、家康の側室である於愛の方が死去(『家忠日記』)。死因は分かっていない。一般的には病死とされるが、異説として毒殺されたなどの他殺説もある。
同年7月20日、前年に下された秀吉の裁定に基づき、沼田城(群馬県沼田市)が真田氏から北条氏の手に渡った(「市谷八幡神社文書」)。氏政あるいは氏直の上洛を促すため、分割された沼田領は北条氏に優位な形をとったらしい。引き渡しには秀吉の使者が立ち会い、徳川家家臣の榊原康政(さかきばらやすまさ)も同席している。
沼田城に城代として入城したのは北条家家臣の猪俣邦憲(いのまたくにのり)だった(「真田家文書」)が、秀吉を激怒させる事件が起こったのは、この配置後、まもなくのことだった。
- 1
- 2