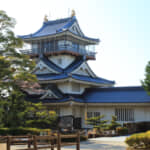小牧・長久手の戦いの「勝者」はどちらだったのか?
史記から読む徳川家康㉝
翌1585(天正13)年1月19日、秀吉は摂津国有馬(現在の兵庫県三田市)にて茶会を開いている。招かれたのは茶人の千利休(せんのりきゅう)や津田宗及(つだそうぎゅう)のほか、徳川家老臣・石川数正の名も見られる(『宗及茶湯日記』)。
同年7月11日、関白職を巡って争いがあることに目をつけた秀吉は、争論に介入することで自身が関白に就任するという異例の昇進を果たしている(「足守木下家文書」「近衛家文書」)。
一方、家康は同年7月に北条氏との盟約に伴い、上野沼田城(群馬県沼田市)を引き渡すよう真田昌幸(さなだまさゆき)に命じたが、昌幸はこれに従わず、両氏は対立(『三河物語』)。昌幸が徳川方を離れ、上杉氏に従属することを表明したため、家康は真田氏の居城である上田城(長野県上田市)の攻撃を開始した。
しかし、老獪な昌幸の戦術に翻弄され、徳川軍は敗退。閏8月2日にも総攻撃を仕掛けたが、やはり撃退されている(「恩田等宛真田信幸書状」)。この背景には、秀吉の意を受け、上杉景勝(うえすぎかげかつ)が援軍を出すなどして応じたことがある。9月下旬には、徳川軍は兵を引き揚げた。
なお、昌幸は対陣中に秀吉に庇護(ひご)を求める書状を送っており、同年10月17日に委細承知した旨の返信が来ている(「真田昌幸宛羽柴秀吉書状」)。
家康が上田城攻略で失敗続きだった8月26日には、秀吉の攻撃を受けていた越中の成政が降伏している(「三村文書」)。
その後、秀吉は朝廷から豊臣姓を下賜された(「押小路文書」)。同年9月9日のことだった。改姓の勅許は翌1586(天正14)年12月の説がある。
同年10月28日、家康は家臣を浜松に集め、協議の席を設けている(『武徳大成記』)。内容は、秀吉に於義丸以上に人質を差し出す必要があるか否かを話し合うものだったようだ。秀吉が同年6月に越中攻めを始める際、家康と成政の関係性を考慮した信雄が、さらなる人質を差し出すよう提示してきたことへの対応を協議したらしい(「久能山東照宮文書」)。
同年11月13日、石川数正が妻子を連れて秀吉のもとへ出奔するという事件が発生する(『武家事紀』)。出奔の動機については、家中の大半が対秀吉の強硬策に傾くなか、和睦を訴えて孤立したため、と見られているが、詳細は明らかではない。実は徳川方のスパイとして秀吉の懐に飛び込んだとする筋立てが小説やドラマなど創作の世界で見られるが、裏付ける史料はない。
数正ほどの重臣が敵方に渡るということは、徳川軍の軍事機密が筒抜けになったということに等しい。ここからしばらく、徳川家は軍体制の大幅な立て直しを強いられることとなった。
- 1
- 2