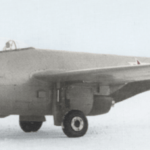のちに世界的傑作戦闘機の血を受け継ぐことになる凡作【ノースアメリカンFJ-1フューリー】
ジェットの魁~第1世代ジェット戦闘機の足跡~ 【第20回】
ジェット・エンジンの研究と開発は1930年代初頭から本格化し、1940年代半ばの第二次世界大戦末期には、「第1世代」と称されるジェット戦闘機が実戦に参加していた。この世代のジェット戦闘機の簡単な定義は「1950年代までに開発された亜音速の機体」。本シリーズでは、ジェット戦闘機の魁となったこれらの機体を俯瞰(ふかん)してゆく。

飛行中のノースアメリカンFJ-1フューリー。ご覧のようにお世辞にも「カッコいい」ジェット戦闘機とは言えず、性能もそれなりだった。艦上機として設計されたにもかかわらず、主翼折畳機構を備えていない。代わりにヴォートF6Uパイレーツと同様に、機首を大きく下げて機尾を持ち上げ、前の機体の機尾の下に後ろの機体の機首を入れて駐機面積を狭めることで、スペースを稼ごうと考えられていた。
アメリカは第2次世界大戦開戦後、ジェット機の未来の可能性が明確になると、ジェット機とジェット・エンジンの研究開発を一気に推進させる方針をとった。特に同盟国で「ジェット機先進国」だったイギリスとは、親密な協力体制を構築していた。
そのような状況下、アメリカ海軍航空局は複数の航空機メーカーに対して、ジェット艦上戦闘機の要求性能を提示し、各社に並行的な研究・開発を行わせた。これは、国内航空機メーカーのジェット機の研究・開発を推進する目的が含まれた措置であった。
受注した航空機メーカーのひとつに、イギリスからの依頼で傑作レシプロ戦闘機P-51マスタングを設計した、当時はまだ新興だったノースアメリカン社があった。そしてほぼ同時にマクダネル社とヴォート社にも同様の発注がなされ、前者はF2Hバンシー、後者はF6Uパイレーツを生産することになる。
ノースアメリカン社では、開発期間の短縮と信頼性が高いという理由から、主翼と尾翼に加えてキャノピーをマスタングから流用。ゼネラル・エレクトリック社が開発を主導し、アリソン社が量産を担当したJ35軸流型ジェット・エンジンを搭載した太い胴体にそれらを取り付けた。
FJ-1フューリーと命名された機体の初飛行は1946年11月27日。初着艦は1948年3月10日のことで、空母ボクサー艦上で実施された。一方で発艦は、本機の場合は飛行甲板上の滑走距離が確保できればカタパルトなしでなんとか可能だった。しかし重量があるジェット機に関しては、発艦時にカタパルトがあればより有利なことを証明した。
なお、主翼にはダイブ・ブレーキが装備されたため折畳機構は設けられなかった。
極初期のジェット機の常で、とりあえず実用上の問題がなければ低性能でも一定数を生産してジェット機運用経験の蓄積に供するという意味合いから、当初は100機が発注された。しかしすぐに30機に減らされて、FJ-1フューリーの総生産機数は、最終的に試作機も含めた33機であった。
なおFJ-1フューリーは、このあと新技術の導入によって全く別の機体に生まれ変わることになる。