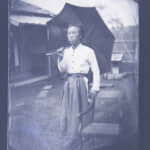【江戸の絵師列伝】肉筆浮世絵で江戸庶民の心を掴んだ元祖浮世絵師・菱川師宣の功績
記念切手にもなった肉筆浮世絵の傑作「見返り美人」。この作品の作者は、現在海外でも評価の高い浮世絵を生み出した人物だった。
■国内外で高く評価され続ける浮世絵の巨匠
皆さんは、「見返り美人」というと何を連想するだろうか。かつてマニアの間で高額取り引きされていた切手を思い出す人も多い事だろう。昭和24年(1949)11月1日に発行された縦67㎜、横30㎜と日本一大きな切手だ。この「見返り美人」と「月に雁」は、日本初の記念切手である。それだけでなく、ここに描かれている美人画は日本の美術史史上で大変重要な作品なのだ。
これを描いたのは菱川師宣である。菱川師宣は寛永7年(1630)に現在の千葉県安房郡鋸南町で生まれたと伝わる。父親は縫箔師という生地に刺繍をしたり、箔をつけたりする職人だったそうだから、子どものころから絵に触れる機会があったのだろう。幼いころから絵を描くことが好きで16歳ごろ江戸に出て、当時人気のあった土佐派の絵を模写するなどして腕を磨いたらしい。そのうち版元から挿絵仕事を貰うようになり、寛文12年(1672)の『武家百人一首』からはクレジットが表記されるようになった。つまり、一人前の絵師と認められたのだ。
挿絵は本の内容への理解を深めるために描かれるのが一般的だ。しかし、生きている女性の姿を写し取ったような師宣の絵は人気が高く、もっともっと絵を見たいという人々の要望に応えるうちに文字がほとんど入らず、見開きで挿絵が掲載されるようになった。このように文章は絵の説明程度という本が出版されていったが、絵が中心の本だからこうした本は「絵本」と呼ばれる。現在は子ども向けの絵本が一般的だ。しかし、江戸時代には大人向けの「絵本」も多く作られた。菱川師宣は『古今役者物語』や『吉原恋の道引』といった大人向けの絵本を数多く手掛けた。生涯に100冊以上の絵本が出版されたといわれる。たくさんの本が作られたということはそれだけ師宣の人気が高かった証左であろう。
やがて、本ではなく絵を一枚で刷って売り出されるようになった。これが現在の私たちが思い浮かべる浮世絵の誕生である。説明の文章もなく、一枚の絵だけを売り物にするためには作品に魅力がなくてはならない。「師宣の美人こそ江戸女」と称されるほど菱川師宣の絵は人々にとって、金を払ってでも手に入れたいものだったのだろう。
ちなみに浮世絵とは浮世の人、つまりその時代に生きる人々を描いた風俗画のこと。浮世絵は木版で刷られた版本の挿絵、木版で刷られた1枚絵、肉筆画(絵師の直筆画)の3つに分けられる。菱川師宣はこのうち、現在の私たちが浮世絵=木版で刷られた一枚画を最初期に手掛けた絵師となった。そのため菱川師宣を浮世絵の開祖とするのが一般的だ。
浮世絵師の祖とされる師宣は、版本の挿絵、一枚ものの浮世絵だけでなく肉筆の世に浮世絵を残している。その代表的な作品が、最初に紹介した「見返り美人」なのである。普通美人画といえば、女性の顔がよくわかるように描かれるが、これはちらっと見えるだけだ。しかし、腰を捻ったしぐさが女性の色気を感じさせる。このポーズは、当時流行していた着物の柄や帯の結び方などがわかるように描いたためこうなったともいわれている。
さらに実子の菱川師房をはじめ、菱川師永、菱川師喜などの多くの弟子を育て菱川流の祖となった。弟子たちとともに多くの作品を作り出し浮世絵を世の中に広めることにおおいに貢献したのである。浮世絵師を語る上で、菱川師宣は外すことができない最重要人物なのだ。

見返り美人
描かれた女性の髪型は当時流行した玉結び。着物にはやはり流行していた大輪の菊と桜の「花の丸模様」が描かれている。帯は、人気役者上村吉弥が火付け役となった「吉弥結び」で結ばれている。このように最先端の流行を写し取ることができたのは、自身のルーツが着物を装飾する縫箔師であったからであろう。
東京国立博物館/ColBase