豊臣秀吉の正室・北政所ねね(高台院)没後400年をしのぶ記念展が開催!高台寺掌美術館展示情報
歴史の「if」を夢想される、木下延由と愛刀「似心」の背負う物語を観に行こう!
高台寺を開創した豊臣秀吉の正室・北政所ねねの没後400年にあたる2024年、高台寺掌美術館で豊臣氏の「続きの 物語」に想いを馳せる展覧会が開催!展示テーマや足を運ぶ前の予習情報をお届けします。
北政所ねね様四百年遠忌記念
「似心(いしん)」木下延由(きのしたのぶよし)の心こころは誰だれに似る?
―国松(くにまつ)伝説を背負(せおった)男の愛刀(あいとう)、京へのぼる―
◆展示テーマ

©高台寺掌美術館
慶長20年(1615) 大坂夏の陣、豊臣秀頼は自軍の敗戦を受け入れ燃え盛る大坂城にて生母の淀殿とともに自刃しました。この時、高台院ねねは高台寺の時雨亭の二階から、大坂城上空が赤く染まるのを見つめていたともいいます。大坂城落城後、秀頼の子・国松は京都で捕縛され、六条河原で処刑されました。処刑時、国松はわずか6歳でした。
これが天下人・豊臣秀吉が低い身分から糟糠の妻・ねねと築き上げた「豊臣」の終焉として知られる歴史の物語です。
しかし、大坂夏の陣に、豊臣の“続き”の物語があったとしたら…?
2020年、一振の刀が発見されました。銘により豊後国立石領初代領主・木下延由が所持していたことがわかりました。延由については資料が乏しく、その実像については不明な点が多くありました。なによりも延由には自身の素性に関わる最大の謎がありました。
「国松伝説」として知られるその謎は延由が大坂夏の陣後、六条河原で処刑されたはずの秀頼の子・国松だというものでした。
優れた名工の手による大名道具にふさわしい延由の刀には持ち主の名前のほかに「似心」という文字が切られています。似心 — 似せる心、とも理解できるこの言葉の表すところは不明ですが、国松伝説の当事者である延由が持つことに大きな意味があるのは間違いないようです。
はたして延由は豊臣国松なのか?
2024年、大坂夏の陣からおよそ410年、国松にとっては祖母に、延由にとっては大叔母にあたるねねの没後400年を機に、国松伝説を背負った男の愛刀が京へのぼります。
◆解説 (日出町歴史資料館・帆足萬里記念館 館長 平井義人)

©高台寺掌美術館
刀の伝来 木下延由(きのしたのぶよし)所持銘のある小太刀「似心」は、令和2年兵庫県赤穂郡にお住まいの所蔵者から連絡をいただき発見されました。所持銘の「木下延由」が、豊後(ぶんご)の国日出藩(ひじはん)に関係のある人物ではないかと推測されたとのこと。刀は収集品であり、若い頃にとある家で目にしたものを後に市場で見つけ、その姿の美しさから迷わず手に入れたのだそうです。刀の本来の所蔵者は豊後国立石領(たていしりょう)主木下家。よって本刀は少なくとも幕末期までは、国元の立石陣屋(大分県杵築市山香町大字立石)か、江戸の木挽町上屋敷(中央区築地一丁目)のいずれかに伝来したのではないかと考えられます。ところが、同家は大正期に京都で父娘が亡くなり断絶した模様で、それを契機に史資料類が四散してしまったものと思われます。最近の調査では、戦後間もない頃同家の菩提寺である長流寺(杵築市山香町大字立石)に、販売を目的に立石領主の刀が持ち込まれたことがあった模様で、それが本刀だったのかも知れません。
木下延由とは 木下延由は日出藩初代藩主木下延俊(きのしたのぶとし)の四男。長男・次男が早世であったため、側室の子三男俊治(としはる)が早い段階から世嗣となったのに対し、同じ側室の子であり年齢も一月程も違わない延由は藩主延俊の死期に至って五千石の分知が決まったとなっています。この延由には、不可解な点も多く、幕府には諱を延次と届けられている点、母の素性がほとんど分かっていない点、熊本藩細川家との結びつきが強く、細川の史料からは藩主細川ほそかわ忠ただ利としが寛永12年(1635)の参勤の折、わざわざ日出藩領の港深江に立ち寄って延俊・延由父子に面会を試みている点、などが挙げられます。幕臣榊原職直(さかきばらもとなお)に宛てた細川忠利の書状では、実際に忠利は深江に立ち寄ったことが確認でき、そこでははじめからの計画でありながら、日和が悪く深江に風待ちのため寄港せざるを得なかったと記されています。延由は寛永19年(1642)5月9日に五千石を分知され交代こうたい寄合よりあいに列することになりますが、明暦4年(1658)7月6日に江戸で死去します。延由と日出藩を継いだ俊治とは分知後全く交流がなく、延由の死は本藩の日出には報告されず、後年に知らされたと記録されています。
国松伝説とは 日出藩に伝わる国松伝説(くにまつでんせつ)とは、日出藩から五千石を分知され立石領主となった木下延由が、実は大坂夏の陣で亡くなった筈の豊臣秀頼(とよとみひでより)の子国松であるとする伝承です。この伝承は、日出藩主家の末裔第18代の木下俊熈(きのしたとしひろ)が著した『秀頼(ひでより)は薩摩(さつま)で生いきていた』で紹介されたものです。同書によると、日出藩には「一子相伝(いっしそうでん)」と言われる伝承が藩主から世嗣のみに口頭で伝えられてきており、明治に入ってその伝統が崩れ、俊熈は日出の木下家屋敷(現金光教日出教会)にて祖母
綾子(あやこ・第16代藩主俊愿(としまさ)の正妻)から、伝授されたとのこと。残念ながら同書には伝授され暗記させられた伝承の文面そのものは記されていないのですが、そこには、鹿児島に逃れた後、秀頼の死を契機に国松は日出藩に預けられ五千石を分知されて立石領主になった、と説かれています。
勿論正史では、秀頼は大坂城で自害し、国松は逃れた京都にて捕らえられ処刑されたとなっていますが、国松が京都で捕らえられたように、大坂城から落ち延びた者は多く存在しているのです。当時のイギリス商館長リチャード・コックスが書き残した公務日記には、夏の陣が終結した数ヶ月後に、江戸幕府は全国の都市に役人を派遣し、不審な人物が匿われていないかを調査して回り、イギリス商館のあった平戸にも調査が入った、と記されています。秀頼の死体が発見されないため、江戸幕府があせっていたことは事実だったのです。

©高台寺掌美術館
小太刀「似心」 茎(なかご)指し表に「木下氏延由所持」という所持銘の入った小太刀。鎬(しのぎ)地の幅が平地よりも広く、両切刃造(りょうぎりはづくり)と分類すべきか。その幅広の鎬地に二筋樋(ひ)が彫られています。現所蔵者によると、作は埋忠明寿(うめただみょうじゅ)と伝えられているとのことですが、定かなことはわかりません。ただ、板目いため肌に杢目(もくめ)肌が交じる地肌は精美で、刃文は焼き幅の狭い直刃すぐはを焼き入れていますが刃中にも鍛え肌が表れており、変化に富み刀工の技量の高さがうかがえます。年代は桃山時代から江戸時代の初期と考えられ、所持銘とともに切られた「似心(いしん)」という文字は「似せの心」あるいは「心を似せる」という意味なのか、所持者延由の置かれた境遇にかかる何らかの「心」の内を表しているのではないかと想像をかき立てられます。
豊後国日出藩 豊後国(ぶんごのくに)日出藩(ひじはん)初代藩主木下延俊(のぶとし)は、豊臣秀吉の正室高台院(こうだいいん・ねね)の兄木下家定の第3子。義兄の細川忠興(ただおき)や叔母の高台院の助力もあって、関ヶ原戦1年後の慶長6年(1601)に、ようやく細川忠興領を割り割く形で日出に三万石を与えられました。父家定もそれに先立ち備中(びっちゅう)足守(あしもり)に二万五千石を与えられています。ところが、慶長19年からの大坂の陣では、その前年まで参勤交代の途上立ち寄って挨拶を交わすほどの強い主従関係を守った豊臣秀頼を裏切り、幕府側に立ち戦いに加わざるを得ませんでした。よってこの戦いで豊臣家が滅んだ事実は、延俊にとって裏切りに対する深い後悔の念を抱かずにはいられなかったと思われます。その後この木下2家のみが、徳川政権下にあって、豊臣を名乗ることができる大名として残ったのです。ただし、日出藩成立期には、幕府への遠慮のためか豊臣ではなく「豊富」の文字を使い鳥居の寄進などが行われました。
【展示会概要】
名 称: 北政所ねね様四百年遠忌記念「似心」木下延由の心は誰に似る?―国松伝説を背負った男の愛刀、京へのぼる―
会 期: 令和6年10月25日(金)~12月23日(月)
開館時間: 午前9時から午後9時10分(入館は午後9時まで)
12月16日(月)以降は午後5時10分(入館は午後5時まで)閉館
会 場: 高台寺掌美術館
〒605-0825京都府京都市東山区高台寺下河原町530
TEL:075-561-1414
入 館 料 : 高台寺の拝観料で入館可能(大人600円、 中高生250円)
圓徳院との共通券 大人900円のみ
掌美術館のみ 大人300円のみ
KEYWORDS:
過去記事
-
-150x150.jpg)
『パンのまち』神戸でSDGsな古代小麦プロジェクト!アイ工務店をはじめ地元企業とそこで働く“人々の縁”が紡いで完成したパンが子ども食堂で提供
-

おじゃる丸×光る君へコラボスペシャル「ヘイアンチョウまったりホリデイ」が放送決定!
-
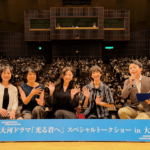
紫式部ゆかりの地・滋賀県大津市で大河ドラマ「光る君へ」スペシャルトークショーを開催!吉高由里子さんと見上愛さんが登壇
-
-150x150.jpg)
本日「光る君へ」クランクアップを迎えた一条天皇を演じる塩野瑛久さんインタビュー!もがき苦しんだ撮影期間のふりかえりや役作りとは?
-
3-150x150.jpg)
大河ドラマ「光る君へ」でききょう(清少納言)を演じるファーストサマーウイカさんへインタビュー!SNSの反響通り「生まれ変わり」と言われても、大げさだとは思えないほどピッタリなキャラクターに親近感


