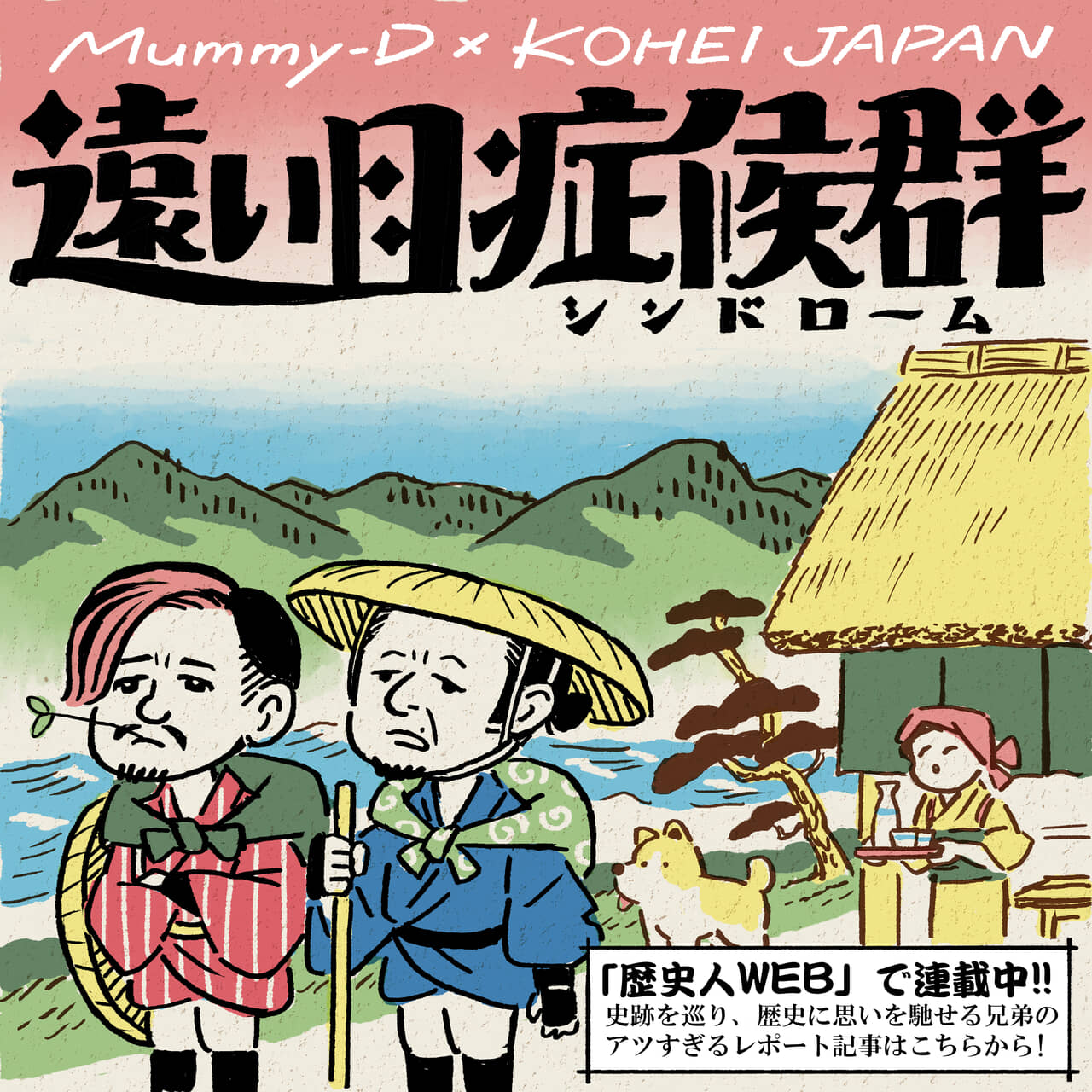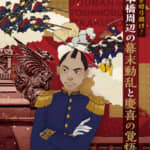五街道の起点・日本橋に息づく江戸情緒 過去と現代が交差する歴史の道を歩く!
Mummy-D&KOHEI JAPANの遠い目症候群#04
■江戸の食を支えた魚河岸発祥の地 日本橋魚市場
(by KOHEI JAPAN)
今では豊洲の市場も定着してきたけど、その前は言わずもがなの築地、築地の前はなんと日本橋だったと。しかもその歴史は実はかなり古く、正式に官許になったのは1674年、そこから1923年の関東大震災後の東京改造計画で築地に移転が決定、からの反対運動などで移転完了に10数年かかったと。
ということは、江戸、明治、大正、昭和の初期まで、ざっと250年以上も魚市場は日本橋にあって、江戸っ子たちの胃袋を満たしてきたのか。それを考えると築地はたった80年くらい。ちなみに関係ないが「笑っていいとも」は31年だ。

日本橋の袂にひっそりと存在する、知る人ぞ知る超重要歴史スポット。魚河岸は江戸っ子たちの食文化を支えていました。
撮影:Mummy-D
捕れた魚介類を集荷あるいは販売する、という点でも日本橋が最も優れた場所だったのだろう。日本橋川を下れば隅田川を経由してすぐ東京湾。東京湾の捕れたての魚介類を、水運を利用して、江戸市中に大量に素早く運び、新鮮な状態で販売できる、そんな場所なのだ。当時は相当な活気だったのだろう。人々の往来、川は荷を運ぶ平田船でごった返し、魚を売る掛け声、舞い上がる土埃、立ち込める潮や魚の匂い……。遠い目をするタイミングだがここ日本橋、とにかく建物が乱立し、川の上はすべて高速道に覆われ、遠い目をするにはなかなかのスキルを必要とされる。
日本初の魚市場、そもそものはじまりなのだが、ここで我ら遠い目症候群クルーたちの知識と繋がった。それは「遠い目症候群」の第1回目「佃島」編だ。
そもそものはじまりを色々調べると、徳川家康が江戸入府のとき、一緒にやって来た摂州佃村(現大阪市西淀川区佃)の森孫右衛門一族の漁師らは佃島を与えられ、江戸近辺での漁業権を握ったと。その見返りとして彼らは毎日、江戸城に魚を納めたのだが、あるとき、残った魚を売ることを許され、日本橋のたもとで販売した──。これが日本橋魚河岸の起源であると。
佃島、やはり都内ではひっそりとしたスポットではあるが、江戸から現代にも密接に関わる重要なスポットなのだと改めて認識。そして昔と比べて魚離れしてゆく現代の日本に、森孫右衛門一族は何を思うのだろうか?遠い目。
後編に続く!
※次回は4月中旬更新予定です。
- 1
- 2