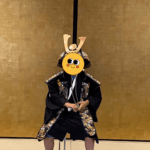タイパ重視の時代だからこそ学びたい!縄文人たちの〝ていねいな暮らし〟
古代のきほん
縄文の遺物のなかには、私たちの心を揺さぶる、ユニークな造形や高い技術に目を見張る品々がたくさんあります。そうした品々を通して、縄文の人々の精神世界を一緒に調査してみよう!
前回、土器や半栽培など、縄文人の驚くべき知恵についてご紹介しました。
今回は、縄文時代に花開いた芸術について掘り下げます。
「縄文時代に芸術なんてあったの?」
「美しいものや、クリエイティブなものなんてあるの?」
そう思われるかもしれませんね。
確かに縄文の人々も、自分たちが作ったものが芸術だなんて思っていなかったでしょう。
でも、彼らが作ったものの中には、現代アートと比べても遜色(そんしょく)ないものだってありますよ。
■現代の芸術家たちも虜になった!火焔型土器の芸術性

火焔型土器(出典:colbase)
縄文時代の人々は、そのあとの弥生時代と違って、同じ形の土器を大量生産したりしませんでした。
きっと縄文芸術家は一つ一つの作品にこだわりを持って、創作していたのでしょう。
その最高峰ともいえる傑作が、火焔型土器(かえんがたどき)です。
燃え盛る炎のような突起がとてもダイナミックです。
縄文土器唯一の国宝で、日本美術の原点とも言われています。
昭和の大芸術家である岡本太郎さんはこの土器に魅了されました。
彼は、「俺が縄文土器を発見した」と言ったそうです。
もちろん土中から発見したのは別の人でしょうが、縄文土器に美術的な価値を発見したのは岡本太郎さんでした。
「芸術は爆発だ」という彼の言葉は有名ですが、燃え盛る炎のようなこの土器を意識していたのかもしれませんね。
ちなみに火焔型土器は実際に使用されたらしく、焦げ跡が残っています。
デザインは素敵ですが、実用性にはちょっと欠けるので、神に祈りを捧げる儀式に使ったのでしょう。
■約5500年前の漆器からひも解く、縄文人の〝おおらか精神〟

鉄石英・赤色顔料入り土器・漆が付着した土器(出典:JOMON ARCHIVES)
木で作った器に漆(うるし)を塗ったものを、漆器(しっき)といいます。
現代の私たちも上品な朱や黒の漆器を使いますが、驚くべき事に、縄文時代から存在していたんです。
一番古い漆器は、青森県の三内丸山遺跡から発見された大皿で、5500年くらい昔のものです。
鮮やかな朱塗りが残っているだけでなく、底には高台(こうだい)もついていて、高い制作技術がうかがえます。
漆は、漆の木から採取して顔料と混ぜて使います。
縄文時代の顔料は、黒は煤などで、赤はベンガラと呼ばれる、土から採った天然の顔料でした。

亀ヶ岡の漆塗り土器(©さらうえ さら)
晩期には、「本当に縄文時代に作られたの?」と疑うほど、独創的なデザインの漆塗り土器が現れます。
青森県の亀ヶ岡遺跡で発見された漆塗りの土器には、黒漆を背景に赤漆が躍動する、大胆なデザインが描かれています。
縄文人の力強くおおらかな精神世界が、うかがい見える気がします。
■縄文人だってオシャレは欠かせない!出土品から見るファッション事情

ヒスイ製大珠(出典JOMON ARCHIVES:)
最後はファッションについてです。
冬や、寒い地方では、やはり暖かい毛皮が一番です。
縄文時代、最も使われていたのはシカやイノシシの皮でしょうが、ラッコやアザラシ、ウサギ、ムササビ、ひょっとしたらサケも使っていたのでは、という人もいます。
縄文時代の遺跡からは動物の骨で作った縫い針も見つかっていますから、縫い合わせて着ていたのでしょう。
また、編布(あんぎん)と呼ばれる布も出土しています。麻、カラムシのような植物繊維を撚(よ)って糸を作り、布を作っていたのです。
この布を使って上衣やズボンを作っていたのでしょう。
服のデザインは分かっていませんが、土偶を参考にして復元すると、とってもオシャレなものになります。
赤や黒で、渦巻き模様などを大胆に作っていたかもしれません。
植物繊維でレースのようなものを作っていたのでは、という人もいます。

漆塗櫛(出典:JOMON ARCHIVES)
オシャレは服だけではありません。縄文女性は髪を結い、櫛やかんざしで飾っていました。他にも、ピアスのような耳飾りをつけ、首には首飾り、腕には貝の腕輪をして、現代の私たちと同じようにファッションを楽しんでいました。
【今回のまとめ】
縄文時代、人々はみすぼらしい服をまとって、生きるだけで精一杯の生活をしていたように思われがちです。
けれど案外、時間に追われる現代人よりも、たっぷり時間をかけて、豊かな精神性や美意識を表現していたのかもしれません。
彼らの遺した品々は、現代の私たちの心を揺さぶり、忘れかけていた大切なものを思い出させてくれる気がします。
とかく現代社会では、効率アップや、タイムパフォーマンスの重要性が主張されがちですが、心の豊かさは忘れずにいたいものですね。
◎参考文献
「三内丸山の世界」山川出版社 岡田康博、小山修三編
「縄文人に学ぶ 歴史・環境・ライフスタイル」地歴社 山尾一郎
「かわいい古代」カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社、光村推古書院書籍編集部譽田亜紀子
「日本の霊性」 新潮社 梅原猛