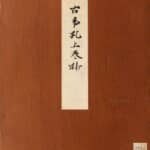『日本書紀』で“呼び捨て”にされているヤバい神・天若日子とは? 朝鮮からの渡来人だった?【古代史ミステリー】
鬼滅の戦史㊱
「天邪鬼(あまのじゃく)」という言葉は、さしたる理由がなくても我を通すタチが悪い人物を指すものとして今日でもよく知られている。しかし、その起源をたどってみると実は古代にまで遡ることは案外知られていない。今回は、歴史と神話を通して天邪鬼の存在を探ってみる。
■我を押し通す「ひねくれ者」?
天逆毎-238x300.png)
天逆毎(あまのざこ)『今昔画図続百鬼』鳥山石燕筆 国立国会図書館蔵
「あの人は天邪鬼だから、本当に困ったもんだ」
世の「ひねくれ者」は、おおよそ、こんな風に非難されるようである。筆者も、時として、やせ我慢して「大衆に阿(おもね)りたくない」と意固地を張ることもあるから、「天邪鬼」の部類に入るのかもしれない。
ちなみに、広辞苑で天邪鬼を引くと、「わざと人の言に逆らって、片意地を通す者」とある。「人に逆らい、人の邪魔をする」とも記されているから、やはり相当な「ひねくれ者」と言わざるを得ないようである。また、「片意地を通す」とは、頑なに我を押し通すこと。
となれば、人に迷惑をかけることもありそう。そんなところから、大方は鼻つまみ者として敬遠されるのがオチ。ならば、少しは自重すべき…と反省するも、とどのつまりで、またもや天邪鬼な性格が顔を覗かせるから始末が悪い。
ここからは、一般論としての天邪鬼のことについてお話ししたい。この人物のタチが悪いところは、我を押し通すことにさしたる正当な理由がない点である。理由付けは本人にとって意味あることかもしれないが、大抵の場合、それは周りから見て納得できるものではない。
むしろ大勢の人の意に逆らうこと自体に楽しみを見出す…というところに特徴がありそうだ。その特異な性格ゆえ、結果として、その言動および行動に対して、正当な評価をされることはほとんどない。どんな結果になっても卑下されるばかりで、悪者呼ばわりされることも。わかっているけど、性格は変えられないのだ。
■人を騙す邪神あるいは妖怪か?
さて、「ひねくれ者」の人間のお話はこのぐらいにして、ここからは、鬼あるいは妖怪としての天邪鬼のお話である。まずは、名前から見ていくことにしよう。名前の中に、「邪」(よこしま)な「鬼」と記されていることに注目したい。「邪」というから、心がねじ曲がった物の怪の如き存在と見なされるようである。
この鬼、仏教の世界では、煩悩の象徴、または仏法を犯す邪神とみなされ、毘沙門天(多聞天)などに踏みつけられたり、鎧の腹部に押し込められた姿で表されることが多い。仏から見れば、極め付けの悪者なのである。「俺は天邪鬼だから〜」な〜んて、自嘲だか自慢だか分からぬような発言は、仏を前にしては、とても言えたようなものではないのだ。
また、民間説話においては、人を騙す妖怪として登場することが多い。人の真似をしてからかったりするたわいもない妖怪が多いが、中には人を殺してその人になりすまし、そのまま暮らし続けること(瓜子姫/うりこひめ など)もある。人の気持ちを見抜く能力に長けているだけに、騙しのテクニックは抜群。並みの詐欺師など、足元にも及ばないのだ。
比売許曽神社-300x200.png)
天佐具売が天から降臨した場所とされる比売許曽(ひめこそ)神社 藤井勝彦撮影
■天探女にそそのかされた天若日子とは?
この詐欺師紛いの天邪鬼、実はその祖先の名が『記紀』に記されているのをご存知だろうか? それが、『古事記』に記された天佐具売(あめのさぐめ/『日本書紀』では天探女)である。高御産巣日神(たかみむすびのかみ)と天照大御神(あまてらすおおみかみ)に命じられて葦原中国へと降り立った天若日子(あめのわかひこ)に、召使として仕えていた巫女であった。
降臨から8年もたっても復命しようとしなかったことを不審に思った二柱が、伝令として雉(きじ)の雉名鳴女(きぎしななきめ)を地上に舞い降りさせた時のことである。この鳥を目にした天佐具売が、天若日子に「不吉な鳥など、射殺してしまいなさい」とそそのかしたことが不幸の始まりであった。ここでもその性格を、「心のねじくれた」とあえて記すほどだから、相当な「ひねくれ者」。まさに、歴史書に記された最初の天邪鬼が、この天佐具売だったのである。
天若日子は、この巫女の言を真に受けて、天神から授かった天之波士弓(あめのはじゆみ)と天之加久矢(あまのかぐや)を放って、雉を射殺してしまった。放った矢は、雉の胸を突き通し、そのまま天へと射上げられ、ついには安河原にいた二柱のもとにまで飛んでいったという。これを目にした両柱が怒って矢を突き返すや、地上にいた天若日子の胸に突き当たって、たちどころに死んでしまったというのだ。
『記紀』において、天神の名前の後には必ず尊や神などの尊称が付けられるのが習わしであるが、天若日子は呼び捨て状態。天神の名を汚した反逆者と見なされたからだろう。その名前にある「天若」も、読みようによってはアマノジャクと読めなくもない。天若日子もまた、天佐具売同様、「ひねくれ者」だったのである。
ちなみに、『日本書紀』に記された天探女の名前の中に「探」とあるが、そこから「実相を探る」女と捉えられることもある。良く言えば「真意を探る」能力を有した賢い女、悪く言えば「他人の心を探る」イヤ〜な女である。その良い意味に捉えられた天佐具売(天探女)が祀られたのが、和歌山県の白浜にある平間神社とか。ここでは、尊称も付けられた天佐具売命として祀られていることはいうまでもない。
最後に興味深いお話を一つ。一説によれば、天佐具売が天から岩船に乗って降臨したのが、大阪市鶴橋付近の「味原池」(すでに埋め立てられた)だったという。すぐ近くに比売許曽神社(ひめこそじんじゃ)があるが、ここに祀られているのが下照比売命(したてるひめのみこと)。
『記紀』が記す下照比売(下照姫)で、天若日子が妻とした女性である。奇妙なのは、『古事記』が、比売碁曾(比売許曽)の社に鎮まるのを新羅からやって来た阿加流比売(あかるひめ)としている点である。
阿加流比売の夫は、新羅王の子・天之日矛(あめのひぼこ)。となれば、天神・天若日子と天之日矛は同一人物で、新羅からの渡来人だとみなすこともできそうなのだ。
ただし、この辺りの真相は不明のまま。神話という靄の中に、真実が隠れたままになっているのが実情である。いつの日か、スッキリ晴れ渡る日が来ることを願うばかりだ。これに関しては、ひねくれ者の天邪鬼ではなく、「実相を探る」ことに長けた天探女の働きに期待したいものである。

弥五郎どん、弥五郎の里/フォトライブラー-150x150.jpg)

坂上田村麻呂「月百姿音羽山月 田村明神/国立国会図書館-e1611722770207-150x150.jpg)
-150x150.png)