清少納言が『枕草子』にどうしても書けなかった、定子や伊周の悲劇
日本史あやしい話52
NHK大河ドラマ「光る君へ」では、藤原道長(柄本佑)か伊周(三浦翔平)かで次の関白の座を巡る展開となっている。同作では定子(高畑充希)に目を輝かせる清少納言/ききょう(ファーストサマーウイカ)も話題になったが、『枕草子』には当時の政治情勢はどのように記されていたのだろうか?
■伊周が与えた紙が執筆のきっかけだった
-202x300.jpg)
清少納言(ColBase)
清少納言が『枕草子』に書き記した頃の政治情勢はどのようなものだったのだろうか?執筆を始めた時期は明確ではないものの、筆を置いたのは、仕えていた定子が亡くなった1001年頃だったようである。
始まりは、内大臣・藤原伊周(公季との説もあるが)が、妹の定子に当時貴重だった料紙を提供したことが契機となったようである。それに何かを書くよう、定子から勧められたことが始まりであった。
おそらくは、993年の初冬の頃だったのだろう。当時は、まだ道隆が健在で、嫡男・伊周も、蔵人頭から参議、公卿、権大納言を経て内大臣にまで登りつめたばかりという、煌めくばかりの栄華を誇るかのような時代であった。
■定子の没落を記さなかった
ところが、955年に、道隆が飲水病(糖尿病か)がもとで病死。さらに後を継いだ弟の道兼も、直後に病死。道兼の弟・道長が、甥である伊周を飛び越えて右大臣に就任した頃から、情勢が変わり始めた。伊周が花山法皇に矢を射るという長徳の変が決定打となって、出身母体である中関白家が衰退することになってしまったのである。
伊周の妹・定子も一時落飾するなど、彼女の身の回りも激変。定子に仕えていた清少納言も、一時里帰りを余儀なくされるなど、彼女にとっても激動の時代を迎えていたはずであった。
ところが不思議なことに、その頃記され続けていたはずの『枕草子』には、中関白家に襲いかかったこの悲運を明確に示すような記述は見当たらないのだ。本来なら、自身が仕える中関白家の衰退ぶりの一つや二つ書き記してもおかしくないのに、彼女はそれを書き留めることはしなかった。それはなぜなのか? 不思議でならないのだ。
清少納言は定子のことをとてもよく慕っていたといわれる。そういえば、彼女が初めて宮に仕えた頃のこととして、恥ずかしげに戸惑う清少納言を定子が気遣ってくれる様子が描かれている。
となれば、考えられることは一つ。清少納言は、敬慕する定子が悲しむのを恐れて、あえて中関白家に降りかかった災難について触れなかったのではないか。そうとしか考えられないのだ。
定子は第二皇女・媄子内親王の出産直後に崩御してしまうが、その亡骸が葬られた鳥辺野の近くに、清少納言が庵を構えて移り住んだとも言い伝えられている。それが、東山月輪だったとか。
そこで、定子の冥福を祈りながらひっそり暮らしたとの伝承が残っている。清少納言は、主人が死してもなお敬愛し続けたのである。

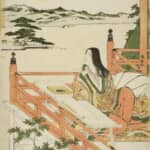


-e1704957789649-150x150.jpg)
-150x150.jpg)
